【日本で約30人】年収100億円の税金シミュレーション|節税対策も解説

日本では所得税が累進課税となっており、最高税率は45%です。
さらに住民税などもかかるため、特に富裕層と呼ばれる方にとっては大きな負担です。
中でも、長者番付でトップに位置する年収100億円を超える場合には、いくら手元に残るのか気になる方もいるでしょう。
この記事では、年収100億円の世界について、税金の種類やシミュレーションを踏まえながら解説します。
資産100億円超の著名人や節税対策もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
年収100億円の世界とは

年収100億円の世界が一体どのようなものなのか、以下に挙げる2つのポイントをもとに紹介します。
- 年収100億円となっている人の割合
- 資産100億円超の著名人
それぞれ詳しく見ていきましょう。
また、100億円を稼ぐための具体的な方法について知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。
【関連記事】100億円稼ぐには?不動産投資のプロが具体的な方法を解説
年収100億円となっている人の割合
年収100億円となっている人の割合は、0.1%にも満たないほどごく少数です。
日本における申告納税者全体の人数は657.5万人で、そのうち所得が1億円を超えるのは1.9万人となります。
さらに所得100億円を超える人に絞ると、わずか28人だけです。
また、2023年に野村総合研究所が公表したデータによると、日本における純金融資産保有額は下表の通りとなっています。
| 種類 | 世帯の純金融資産保有額 | 世帯数 | 割合 | 資産規模 |
| 超富裕層 | 5億円以上 | 11.8万 | 0.2% | 135兆円 |
| 富裕層 | 1億円以上〜5億円未満 | 153.5万 | 2.8% | 334兆円 |
| 準富裕層 | 5,000万円以上〜1億円未満 | 403.9万 | 7.3% | 333兆円 |
| アッパーマス層 | 3,000万円以上〜5,000万円未満 | 576.5万 | 10.3% | 282兆円 |
| マス層 | 3,000万円未満 | 4,424.7万 | 79.4% | 711兆円 |
世帯の純金融資産保有額が5億円以上である超富裕層を見ても、割合は0.2%と少数です。
その中で100億円を超えるとなると、ごく一部に限られていることがよく分かるでしょう。
なお、弊社ゴールドトラストが運営する「100億円資産形成倶楽部」では、100億円の資産を築くノウハウを提供しています。
専門家の支援を受けながら、着実に資産を形成したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
引用:
・財務省|第19回 税制調査会(2022年10月18日)[総19-2]財務省参考資料(個人所得課税)
・野村総合研究所|野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計
資産100億円超の著名人
ここでは資産が100億円を超える、日本の著名人を紹介します。
2025年における日本の富豪TOP10は、下表の通りです。
| 名前 | 企業名 | 資産額 | 年齢 | |
| 1位 | 柳井正 | 株式会社ファーストリテイリング | 7兆円 | 76歳 |
| 2位 | 孫正義 | ソフトバンク株式会社 | 4兆930億円 | 67歳 |
| 3位 | 滝崎武光 | 株式会社キーエンス | 3兆円 | 80歳 |
| 4位 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス株式会社 | 1兆5,200億円 | 79歳 |
| 5位 | 重田康光 | 株式会社光通信 | 1兆円 | 60歳 |
| 6位 | 安田隆夫 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス (旧株式会社ドンキホーテホールディングス) |
7,840億円 | 76歳 |
| 7位 | 高原豪久 | ユニ・チャーム株式会社 | 7,690億円 | 63歳 |
| 8位 | 関家(一家) | 株式会社ディスコ | 7,260億円 | |
| 9位 | 伊藤(兄弟) | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 7,110億円 | |
| 10位 | 森章 | 森トラスト株式会社 | 6,820億円 | 88歳 |
日本では誰もが知るような有名企業に携わる方ばかりで、莫大な資産を保有しているのも納得の結果です。
資産100億円超という値は、並大抵では到達できないような金額といえるでしょう。
年収100億円にかかる税金の種類
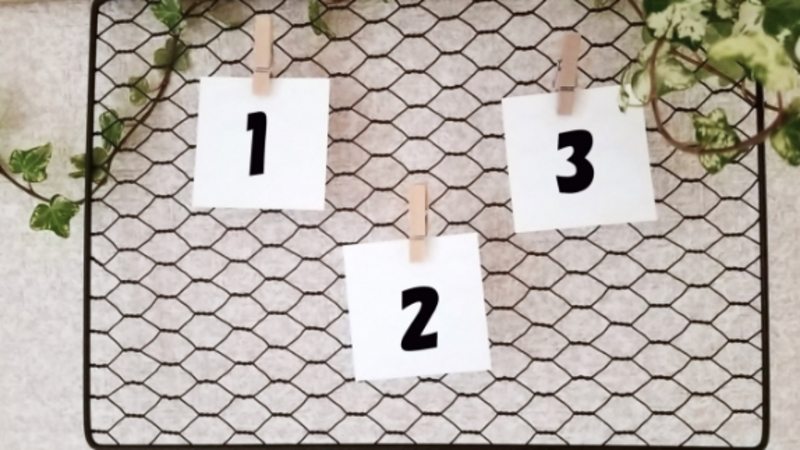
年収100億円にかかる税金の種類は、以下の3つです。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
税金①:所得税
所得税には、以下の3つが存在します。
- 個人所得税
- 復興特別所得税
- 金融所得課税
それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人所得税
個人所得税は、所得が上がるにつれて納税額も増加する超過累進税率となっているのが特徴です。
課税対象は、1月〜12月までの1年間における所得から控除を引いた金額になります。
個人所得税を簡単に求められる超過累進課税の速算表は、下表の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除金額 |
| 1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円〜 | 45% | 479万6,000円 |
超過累進税率では所得全体の税率が上がるわけではなく、定められた金額を超えた分だけが上昇します
なお、日本国内では、所得が1億円を超えると税負担率が逆転する「1億円の壁」が問題となっています。
1億円の壁に関する基礎知識や対処法について詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。
【関連記事】【所得税】1億円の壁とは?増税に負けない資産形成術もわかりやすく解説
復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に向けた財源を確保するために徴収される税金です。
課税対象は2013年から2037年における各年の基準所得税額で、2.1%を掛けた金額が課されます。
ただし、現在は防衛特別所得税への移行が検討されており、法人では「防衛特別法人税」としてすでに導入が決定されています。
個人の特別所得税も2037年までに変わる可能性があるため、今後の動向をチェックしましょう。
防衛特別所得税の税率や影響について知りたい方は、下記の記事もあわせて参考にしてください。
【関連記事】【計算例付き】防衛特別法人税とは?課税対象や企業に与える影響を解説
金融所得課税
金融所得課税は、株式や預貯金などを代表とする、金融商品から得た所得が対象の税金です。
例えば、株式では配当金や譲渡益、預貯金では利子に対して税金がかかります。
税率は20.315%となっており、以下に挙げる3つの合計です。
- 所得税(15%)
- 住民税(5%)
- 復興特別所得税(0.315%)
20.315%の中には、上述した復興特別所得税(所得税15%×2.1%=0.315%)も含まれています。
なお、金融所得課税は超富裕層を対象に、2025年1月1日以降の所得から引き上げられます。
金融所得課税の引き上げがおよぼす影響について知りたい方は、下記の記事もあわせて参照しましょう。
【関連記事】金融所得課税の引き上げはいつから?強化の影響や今からできる対策も解説
税金②:住民税
住民税は、行政サービスの財源として徴収される税金のことです。
学校教育や上下水道などの費用として活用され、都道府県分と市町村分を納める必要があります。
住民税の税額は、下表の通りです。
| 均等割 | 所得に応じて負担 | 所得に対して道府県民税4%+市町村民税6%の合計10% (政令指定都市では、道府県民税2%+市民税8%) |
| 所得割 | 定額の負担 | 道府県民税1,000円+市町村民税3,000円の合計4,000円 |
2024年からは国土や生物保全などの整備に必要となる財源を確保するため、国税として森林環境税1,000円もあわせて徴収されています。
ただし、都道府県・市町村それぞれの判断で税率および納税額を決めているため、あくまで基準として覚えておきましょう。
引用:総務省|個人住民税
税金③:社会保険料
社会保険は、加入することによって医療や年金などの保障が受けられます。
厳密に言えば、日本では税金として扱われていませんが、実質的な役割としては同様です。
主な社会保険料としては、下表の3つが挙げられます。
| 種類 | 保険料率・保険料額 |
| 健康保険料 (2025年度協会けんぽ) |
全国平均:10% (9.62%〜10.78%) |
| 介護保険料 | ・第1号被保険者(65歳〜):市町村ごとに定められた基準額に、所得段階別の乗率をかけた額 (2024年〜2026年における基準額の全国平均は月額6,225円) ・第2号被保険者(40歳〜64歳):全国一律1.59% |
| 厚生年金保険料 | 18.3% |
社会保険料は税金ではないものの、安心して生活するために不可欠であるといえるでしょう。
引用:
・全国健康保険協会|令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
・公益財団法人 生命保険文化センター|公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?
・日本年金機構|厚生年金保険料額表
年収100億円の税金はいくら?税額シミュレーション

年収100億円の税金はいくらになるのか、以下に挙げる4つをもとに紹介します。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
- 手元に残る金額【最終結果】
より分かりやすいよう、課税所得金額を100億円に設定してシミュレーションするので、あくまで目安として参考にしてください。
シミュレーション①:所得税
まず所得税の税額シミュレーションとして、以下の3つを解説します。
- 個人所得税
- 復興特別所得税
- 金融所得課税
それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人所得税
個人所得税の計算方法は、以下の通りです。
| 個人所得税 =課税所得金額×税率−控除金額 =100億円×45%−479万6,000円 =44億9,521万円 |
シミュレーション結果から、所得の半分近くとなる莫大な納税額であることが分かります。
復興特別所得税
復興特別所得税の計算方法は、以下の通りです。
| 復興特別所得税額 =基準所得税額×2.1% =44億9,521万円×2.1% =9,439万9,410円 |
他の税金と比べると税率は低くなっていますが、所得100億円の場合では大きな金額になることが分かるでしょう。
金融所得課税
金融所得課税の引き上げを踏まえた計算式は、以下の通りです。
| {合計所得金額※ −特別控除額(3.3億円)}×22.5%=① ①−基準所得税額(税率15%)=追加で申告納税する金額 |
※株式の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・給与・事業所得・その他の各種所得を合算した金額であり、スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外
所得100億円(事業所得40億円+金融所得60億円)の場合は、以下のように算出できます。
| {100億円−3.3億円}×22.5%=21億7,575万円 21億7,575万円−{基準所得税額26億9,521万円※1}=−5億3,195.4万円 |
※1 {(40億円×45%)−479.6万円}+{60億円×15%}=26億9,521万円
この場合は通常の所得税額が上回っているため追納はなく、基準所得税額は26億9,521万円となります。
金融所得課税のみを抜き出すと、60億円×15%の9億円です。
シミュレーション②:住民税
住民税の計算は、以下の4ステップです。
| ①所得金額=収入金額−必要経費(会社員の場合は「給与所得控除」) ②課税所得金額=①−各種所得控除額 ③住民税額=所得割{②×10%−税額控除額}+均等割4,000円+国税1,000円 |
ここでは所得控除や税額控除を考慮せず、簡易的に算出したシミュレーション結果を紹介します。
| 100億円×10%+4,000円+1,000円=10億5,000円 |
実際に正確な金額を計算したい場合には、控除額を踏まえて算出してください。
シミュレーション③:社会保険料
社会保険料の計算方法とシミュレーションは、それぞれ下表の通りです。
| 計算方法 | シミュレーション結果 | |
| 健康保険料 | 標準報酬月額×健康保険料率(全国平均10%) | 月額6万8,874円 |
| 介護保険料 | 標準報酬月額×介護保険料率 | 月額1万1,051円(40歳〜64歳の場合) |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額×保険料率18.3% | 月額5万9,475円 |
※標準報酬月額には上限があるため、今回は最大の場合を紹介
上記はいずれも、会社と折半した金額となります。
上限が定められている分、年収100億円に対する負担はそれほど大きくないといえるでしょう。
引用:全国健康保険協会|令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京)
シミュレーション④:手元に残る金額【最終結果】
以上のシミュレーションを踏まえて、所得100億円(事業所得40億円+金融所得60億円)で手元に残る金額は約62億円と算出できます。
| 年収 | 100億円 |
| 個人所得税 | 17億9,521万円 ({40億円×45%}−479.6万円) |
| 金融所得課税 | 9億円 (60億円×15%) |
| 復興特別所得税 | 5,659万9,410円 ({17億9,521万円+9億円}×2.1%) |
| 住民税 | 10億5,000円 |
| 健康保険料 | 82万6,488円 (6万8,874円×12か月) |
| 介護保険料 | 13万2,612円 (1万1,051円×12か月) |
| 厚生年金保険料 | 71万3,700円 (5万9,475円×12か月) |
| 【結果】 | 61億9,651万7,790円 |
つまり、全体の約4割もの金額を徴収されており、年収100億円の方にとっても税金の負担は無視できないといえるでしょう。
【税金に負けない】年収100億円の節税戦略

年収100億円の場合におすすめの節税戦略は、以下に挙げる3つです。
- 不動産投資を積極的に活用する
- 金融資産と実物資産のバランスを見直す
- 相続税・贈与税も考慮する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
また、所得30億円超の富裕層における資産形成術や節税対策を知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】所得30億円超の富裕層における現状|さらなる資産形成術や節税対策も解説
節税戦略①:不動産投資を積極的に活用する
不動産投資を活用すると、耐用年数の期間は減価償却分を経費にできるため、所得税の節税が可能です。
1度不動産を購入すると継続的に経費として計上でき、長期的な税金の抑制につながるのです。
減価償却費だけではなく、管理費や修繕費なども経費の対象になります。
また、以下のように、資産管理会社の設立も節税に効果を発揮します。
- 家族への所得分散で所得税を抑制できる
- 経費の対象が広がる
- 所得税よりも最高税率の低い法人税率となる など
なお、弊社が運営する「100億円資産形成倶楽部」では、不動産投資や資産管理会社の設立に関して、専門家のアドバイスを受けられます。
効果的な節税対策で資産形成を実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産投資で経費計上できる項目についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせて参照しましょう。
【関連記事】不動産投資で経費に計上できる12項目|経費にできない3項目も紹介
節税戦略②:金融資産と実物資産のバランスを見直す
金融資産と実物資産の見直しは、節税およびリスク管理の観点からも重要です。
経済状況や世界情勢を踏まえながら、許容範囲内のリスクであるか、ポートフォリオを再考します。
その中でも金融資産の比重を抑えられると、節税にもつながります。
ご自身はもちろん世界の状況も日々移り変わっていくため、ポートフォリオは定期的に見直しましょう。
節税戦略③:相続税・贈与税も考慮する
相続税や贈与税も計画的に対応すると、節税対策につながります。
代表的な例が暦年贈与で、年間110万円以下であれば税金をかけることなく贈与が可能です。
また、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません。
2,500万円を超過した分は1律20%の税率となり、通常の贈与税よりも税金の抑制が実現可能です。
なお、贈与税の基礎知識や税負担を減らす方法について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】資産1億円の贈与税はいくら?税率の早見表や税負担を減らす特例も解説
まとめ:年収100億円は税金の負担も大きくなる

年収100億円は内訳にもよりますが、40%を超えるような税金がかかります。
規模が大きい分、節税対策の効果も絶大となるため、積極的に取り入れましょう。
なお、弊社ゴールドトラストは、お金持ちを増やすためのプライベートサロン「100億円資産形成倶楽部」を運営しています。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】富裕層への課税強化はメリットばかりではない?国内外の現状や節税対策も
【関連記事】【国際比較】各国の金融所得課税|非課税の国も?税の基礎知識とともに解説
【関連記事】【2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い





