【所得税】1億円の壁とは?増税に負けない資産形成術もわかりやすく解説

「1億円の壁」とは我が国の所得税制度において、高所得者ほど税負担率が下がってしまう逆転現象のことです。
特に金融所得の優遇税制が影響しており、所得が1億円を超えた場合に税負担率が軽くなっていく点が問題視されています。
この記事では所得税の基礎知識や最新の増税動向とともに、「1億円の壁」の仕組みを解説します。
増税に負けない資産運用や節税対策の考え方もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
【1億円の壁を理解するために】所得税の基礎知識

「1億円の壁」を正しく理解するために、まず日本の所得税に関して、下記の2点を解説します。
- 課税方式
- 近年における増減税の動き
順に見ていきましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
課税方式
日本の所得税は、所得が高い人ほど高い税率が課される「累進課税方式」を採用しています。
具体的には、課税所得(所得控除後の金額)に応じて税率が7段階に設定されており、最低5%から最高45%まで税率が上昇します。
これに加え、所得税には「復興特別所得税」が2.1%上乗せされます。
復興特別所得税は東日本大震災の復興財源を確保するための税金で、2037年まで課税が続く予定です。
また、住民税は全国一律で10%が課されるため、所得が4,000万円を超える高所得者の場合、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた実質的な最高税率は55.945%にも達します。
このように、日本の所得税は累進課税方式を採用しており、所得が増えるにつれて税負担も重くなる仕組みになっています。
近年における増減税の動き
近年、日本の所得税制度では、防衛費増額に伴う新たな税制改正が検討されています。
特に注目されているのが「防衛特別所得税」の導入です。
防衛特別所得税は現行の復興特別所得税(2.1%)を1.1%に引き下げる一方で、新たに1%の防衛特別所得税を課すものです。
名称が復興支援から防衛費用へと変更される形になり、国民の実質的な税負担は大きく変わりません。
防衛特別所得税は2026年以降の導入が検討されており、今後の国会審議に注目が集まっています。
なお、法人税に関しては、防衛費増額のための増税がすでに決定済みです。
税制改正は、今後も社会情勢に応じて変化する可能性があるため、最新情報を常にチェックしましょう。
防衛特別法人税の税率や対象となる法人に与える影響など詳しい情報を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】【計算例付き】防衛特別法人税とは?課税対象や企業に与える影響を解説
1億円の壁とは
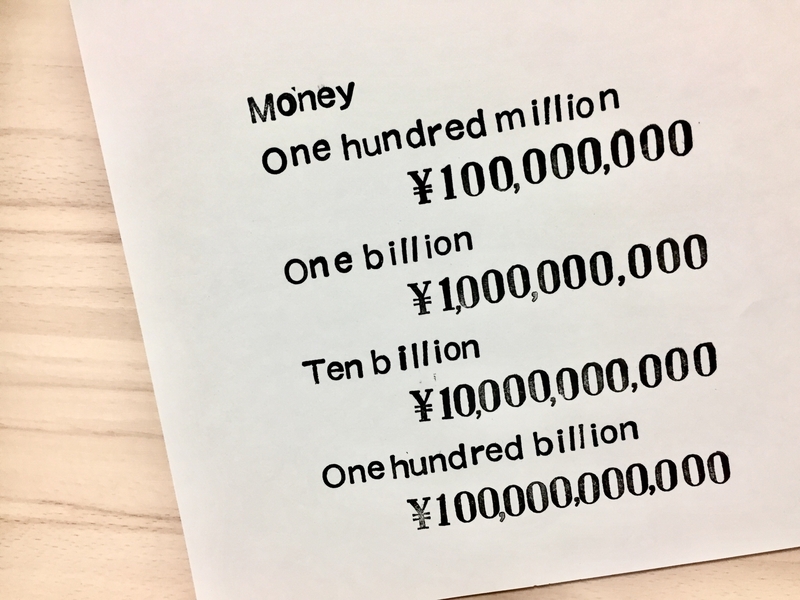
「1億円の壁」とは、日本の所得税制度において、所得が1億円を超えた場合に税負担率が下がる逆転現象を指します。
ここでは1億円の壁に関して、下記の3項目に分けて解説します。
- 定義
- 所得金額1億円超の納税状況
- 問題視されている理由
順に見ていきましょう。
定義
「1億円の壁」とは、所得金額が1億円を超えたあたりを境に税負担率が低下する現象を指します。
通常、所得税は累進課税により、所得が増えるほど税率も上がります。
しかし、所得1億円を超える富裕層では、給与所得よりも株式譲渡益や配当所得などの金融所得が多くなっているのが現状です。
金融所得は他の所得と異なり税率が一律約20%で固定されているため、所得全体に対する税負担率が下表のように下がってしまいます。
| 合計所得金額 | 所得税負担率 |
|---|---|
| 3,000万円 | 21.3% |
| 5,000万円 | 24.7% |
| 1億円 | 27.1% |
| 2億円 | 26.7% |
| 5億円 | 24.0% |
特に1億円前後で負担率がピークに達し、その後徐々に下がっていきます。
これが「1億円の壁」と呼ばれるゆえんです。
所得金額1億円超の納税状況
財務省の資料によると申告納税者全体の人数は約657.5万人で、そのうち年間の合計所得が1億円を超える納税者は約1.9万人です。
全体の約0.3%弱にすぎませんが、納税額は約5.6兆円に上ります。
超富裕層における所得金額の内訳は、下表の通りです。
| 所得の種類 | 割合および金額 |
| 給与所得 | 19.3%(約1.0兆円) |
| 上場株式等の譲渡所得等 | 14.4%(約0.8兆円) |
| 非上場株式等の譲渡所得等 | 27.4%(約1.5兆円) |
| 分離長期譲渡所得 | 21.3%(約1.2兆円) |
| その他の所得 | 17.6%(約1.0兆円) |
特に株式譲渡所得が全体の4割を超えており、金融所得が大きな割合を占めることが「1億円の壁」の構造的な要因となっています。
問題視されている理由
「1億円の壁」が問題視される最大の理由は、同じ所得額であっても稼ぎ方によって税負担が大きく異なる点です。
例えば、すべて給与所得で1億円を稼いだ場合、最高税率約55%が適用される一方、株式譲渡益などの金融所得では約20%の税負担で済みます。
結果的に、実質的な手取り額が大きく異なってしまいます。
また、金融所得による収入は資産運用を前提としているため、もともと資産を多く保有する富裕層が有利になりやすい構造です。
そのため、「働いて稼ぐ人ほど損をする」と言われる不公平感につながり、国会などでも議論の対象となっています。
「1億円の壁」解消に向けて引き上げられた金融所得課税とは

「1億円の壁」の原因となっている金融所得への優遇税制を見直す動きが進んでいます。
特に2025年度の税制改正では、超富裕層を対象にした金融所得課税の強化が決定されました。
ここでは、金融所得課税に関して、下記の3点について解説します。
- 課税対象
- 追加納税額
- 引き上げ時期
順に見ていきましょう。
課税対象
今回の税制改正で対象となるのは、従来低税率で課税されていた「金融所得」です。
具体的には、株式の売却による利益(譲渡益)や配当金などが該当します。
金融所得は従来、所得がいくらであっても一律約20%(所得税15%+住民税5%)の税率で課税されていました。
しかし、所得1億円超の富裕層の多くが金融所得を収入の中心としており、この優遇が「1億円の壁」を生む原因となっていました。
今後は一定額を超える金融所得に対して追加で税率を上乗せする方法、いわゆる「ミニマムタックス」が導入され、超富裕層の税負担が重くなります。
追加納税額
追加納税額の計算方法は、下記の通りです。
| (合計所得金額-3.3億円)×22.5%(税率)-通常の所得税額=申告納税対象 |
合計所得とは株式の譲渡所得だけではなく、新NISAなどの非課税所得を除く給与所得や不動産の譲渡所得の合計です。
なお、現状の金融所得課税の計算式は、下記の通りです。
| 合計所得×15%(税率)=金融所得課税 |
合計所得が10億円・50億円の場合で比較してみましょう。
| 合計所得10億円 | 合計所得50億円 | |
| 従来の課税額 | 10億円×15%=1億5,000万円 | 50億円×15%=7億5,000万円 |
| ミニマムタックス適用後の課税額 | (10億円-3.3億円)×22.5% =1億5,075万円 |
(50億円-3.3億円)×22.5% =10億5,075万円 |
| 追加納税額 | 75万円 | 3億75万円 |
※合計所得がすべて金融所得の場合
※わかりやすいように、税率は金融所得課税のうち所得税の15%とする
このように、合計所得が多くなるほど追加納税の負担額が多くなります。
引き上げられる金融所得課税による具体的な影響や、節税対策のポイントなど詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】金融所得課税の強化とは?推進されている理由や節税対策のポイントを解説
引き上げ時期
金融所得課税の強化は、2025年(令和7年)以降の所得から適用されます。
つまり、実際に納税負担が増えるのは2026年の確定申告からです。
ただし、将来的に金融所得課税の対象範囲や税率がさらに見直される可能性もあるため、資産運用をする人は動向を注視しておくことが重要です。
金融所得課税の引き上げに関して、影響を大きく受ける人や備える方法などより詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】金融所得課税の引き上げはいつから?強化の影響や今からできる対策も解説
1億円の壁は海外でも発生している?

「1億円の壁」のような税負担率の逆転現象は、日本特有の問題ではなく、海外でも一定程度見られます。
各国の所得税制度を比較すると、アメリカやイギリスでは所得に応じた累進課税を採用しています。
しかし、キャピタルゲイン(株式譲渡益)や配当所得に対する税率は最大20%程度と比較的低めです。
これにより、高所得者が資産運用で得た収入は税負担が軽減されやすい状況になっています。
一方、ドイツやフランスでは金融所得に一律の税率(ドイツ26.375%、フランス12.8%+社会保険税17.2%)を適用しつつ、総合課税の選択も可能です。
いずれの国でも金融所得への優遇は一定程度存在し、高所得者の税負担率が抑えられる構造が共通しています。
日本の「1億円の壁」問題は特有の現象ではあるものの、世界的にも資産所得に対する課税のあり方は議論の的となっています。
アメリカやイギリスなど主要国の課税方式や金融所得課税の税率、日本との違いに関して詳しい情報を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】各国の金融所得課税|非課税の国も?税の基礎知識とともに解説
【1億円の壁を突破したい方へ】富裕層に近づく資産形成戦略

富裕層に近づくための資産形成戦略を、5つ紹介します。
- 目指すべき資産保有額を把握する
- 年収を増やす
- 資産運用を始める
- 不動産投資に挑戦する
- 専門家へ相談しながら節税対策も進める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ①:目指すべき資産保有額を把握する
目指すべき資産保有額を把握することは、富裕層に近づく第一歩です。
株式会社野村総合研究所では、世帯として保有する金融資産の合計から負債を差し引いた「純金融資産額」を基準として、下表のように富裕層の分類を定義しています。
| 分類 | 純金融資産保有額(2023年) | 全世帯に占める割合 |
| 超富裕層(5億円以上) | 135兆円(11.8万世帯) | 0.2% |
| 富裕層(1億円以上5億円未満) | 334兆円(153.5万世帯) | 2.8% |
| 純富裕層(5,000万円以上1億円未満) | 333兆円(403.9万世帯) | 7.3% |
| アッパーマス層(3,000万円以上5,000万円未満) | 282兆円(576.5万世帯) | 10.3% |
| マス層(3,000万円未満) | 711兆円(4424.7万世帯) | 79.4% |
富裕層と超富裕層を合わせた世帯数は全世帯の3%ですが、保有している純金融資産保有額は26%とおよそ3割近くとなっています。
目指すべき資産保有額を把握し、富裕層への第一歩を踏み出しましょう。
引用元:株式会社野村総合研究所|野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計
ステップ②:年収を増やす
富裕層に近づくためには、以下のように元手となる資金を増やす必要があります。
- 年収の高い職業に就く(昇進・転職など)
- 副業や事業を始める(ネットビジネス・法人化)
- 投資で資産運用する(余剰資金を活用) など
最も手堅い方法は現在の職場で昇進を目指すか、年収の高い業界・職種への転職です。
しかし、給与所得だけで資産形成を進めるには限界があります。
そこで、副業や事業による収入源を増やすのも効果的でしょう。
ネットショップ運営やブログなどは初期費用が少なく始めやすい点も魅力です。
さらに、得た資金を投資に回して効率的に資産を増やす工夫も欠かせません。
富裕層を目指すには、労働所得と資産運用の両輪での収入拡大が求められます。
ステップ③:資産運用を始める
資産形成を加速するには、貯金だけでは限界があります。
例えば、毎月10万円ずつ貯金をした場合、1億円に到達するには約84年もかかります。
仮に毎月30万円貯金しても約28年が必要となり、いずれも現実的とは言えません。
このような状況を打破するには、資産運用によってお金を「増やす力」を養う必要があります。
資産運用は、労働による収入とは異なり、お金自身に働いてもらう仕組みです。
初心者でも取り組みやすい運用方法を選び、リスクを抑えながら資産を増やしていきましょう。
なお、資産運用を始める際に意識したいポイントは以下の3つです。
- ローリスクの資産運用から始める
- 投資対象や時間を分散する
- iDeCoやNISAを利用して節税する
資産運用の種類やコツについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】資産運用11種類のメリットやリスクを比較!初心者向けのコツも解説
ステップ④:不動産投資に挑戦する
不動産投資は、サラリーマンでも富裕層に近づける現実的な資産形成手段として注目されています。
不動産投資とは、マンションやアパートなどの不動産を購入し、第三者に貸し出すことで家賃収入を得る方法です。
例えば、5,000万円や1億円規模の物件をローンで購入し、25年〜30年かけて家賃収入で返済を続ければ、最終的に大きな資産が手元に残ります。
ローン返済が家賃収入で賄えれば、実質的に他人資本で資産形成が可能になる点も魅力です。
ただし、フルローンが組めるケースは少なく、一般的に購入価格の1割〜3割程度の自己資金が求められます。
とはいえ、それでも自己資金以上の資産を形成できるレバレッジ効果は絶大です。
不動産投資は、本業の収入だけでは難しい資産形成を加速させる手段として有効といえるでしょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは土地・建物がセットになった新しい不動産投資「賃貸マンションアパート(一棟買い):トチプラス」を提供しております。
マンション経営のトータルサポート「分譲型マンション・アパート投資 :エステシア」もチェックして、富裕層への第一歩を踏み出しましょう。
ステップ⑤:専門家へ相談しながら節税対策も進める
資産形成が進んでいくと、避けて通れないのが税金対策です。
特に金融所得や不動産収入が増えると所得税や相続税など、多くの税負担が発生します。
資産を守りながら増やすためには、早い段階から税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家へ相談しながら節税対策も進めましょう。
税金対策は法律の知識が求められ、自己判断ではリスクが伴います。
専門家のサポートを受けることで、節税スキームの提案や税制改正への柔軟な対応が可能になるでしょう。
例えば、不動産投資による減価償却費の活用、法人化による税負担軽減など、多岐にわたる手法が存在します。
富裕層への道は、単に稼ぐだけでなく「いかに資産を守るか」も大切なポイントです。
1億円の壁に負けない資産形成術を知りたい方は
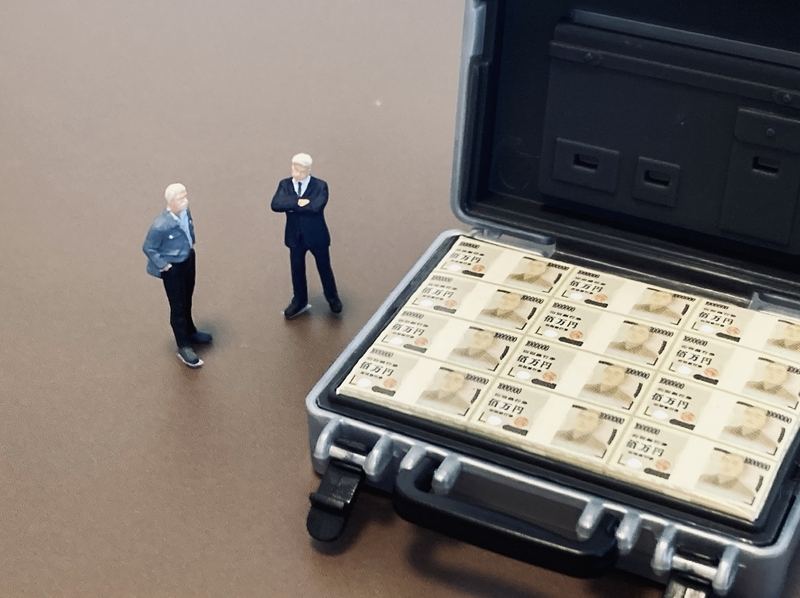
資産形成を効率良く進めたい方には、弊社ゴールドトラストが運営する「100億円資産形成倶楽部」がおすすめです。
同倶楽部は不動産投資を通じて資産1億円・10億円、さらには100億円を目指すための完全会員制サービスです。
創業者自身が築き上げた独自の資産形成ノウハウをもとに、不動産投資の実践方法や節税スキームを学べます。
特に、高い税率が課せられる日本において、税負担を抑えつつ大きな資産を築くための具体的なアドバイスやサポートが充実しています。
資産形成のノウハウを獲得したい方は、100億円資産形成倶楽部をぜひチェックしてみてください。
1億円の壁に関するよくある質問

「1億円の壁」に関するよくある質問を、2つ紹介します。
- 「1億円の壁」とは?
- 「1億円の壁」解消に向けた国の動きとは?
順に見ていきましょう。
質問①:「1億円の壁」とは?
「1億円の壁」とは、日本の所得税制度において、所得が1億円を超えると税負担率が逆に下がってしまう現象を指します。
超富裕層の多くが給与所得ではなく、株式の譲渡益や配当所得などの金融所得を中心に収入を得ていることが原因です。
金融所得は一律約20%程度の低税率で課税されるため、所得が高額になるほど税負担率が軽減される仕組みとなっています。
「働いて稼ぐ人ほど税負担が重い」という不公平感を生み出しており、近年では税制改正の議論が活発化する要因の1つになっています。
質問②:「1億円の壁」解消に向けた国の動きとは?
「1億円の壁」問題に対して、日本政府は2025年度の税制改正で金融所得課税の強化を決定しました。
具体的には、金融所得が3億円を超える部分に対して追加で22.5%(所得税15%+住民税7.5%)が課税されます。
これにより、所得が多いほど税負担が軽減されていたこれまでの構造を是正し、富裕層への課税が強化される形となりました。
また、今後は「防衛特別所得税」の新設など、さらなる税制改正が予定されており、個人・法人ともに税負担が増える可能性が高くなっています。
資産形成を目指す方は、最新の税制動向を常にチェックしておくことが大切です。
まとめ:1億円の壁はわかりやすく言うと「税負担率の逆転」

「1億円の壁」とは、日本の所得税制度において、所得が1億円を超えると税負担率が下がる現象のことです。
特に金融所得への低い税率が原因で、富裕層ほど手取りが増えやすい仕組みになっており、国は金融所得課税の強化など対策を進めています。
1億円の壁を突破すべく資産形成をするには、早めの行動と正しい戦略をバランスよく実践することが必要です。
なお、効率の良い不動産投資のノウハウや、効果的な節税方法を詳しく知りたい方は、100億円資産形成倶楽部のページをご覧ください。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】金融所得課税とは?日本と海外を比較!最新の動きや引き上げのリスクも解説
【関連記事】【2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い
【関連記事】【法人向け】不動産を売却したときにかかる税金とは?計算方法や節税対策も





