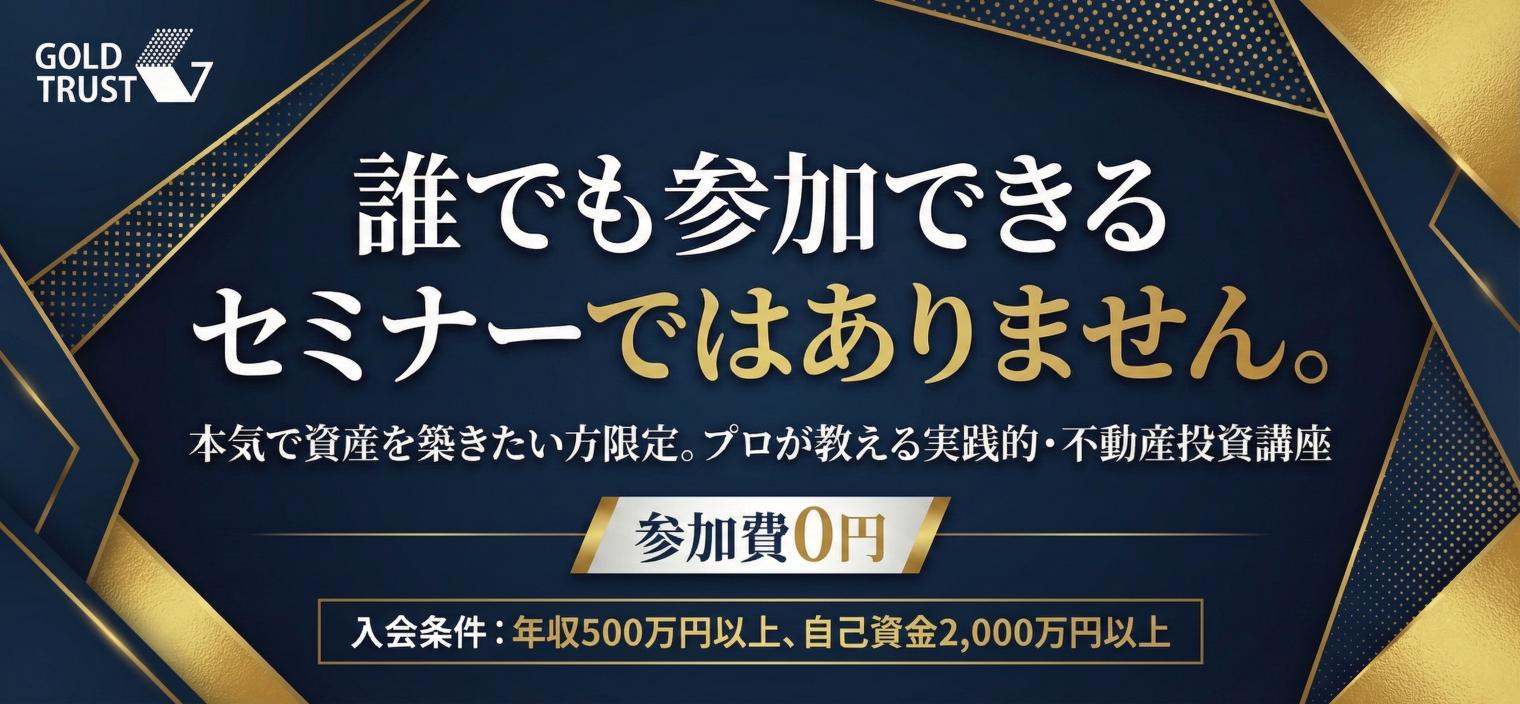【儲かる?】老人ホーム経営の収支構造・利益率|平均年収や成功するコツも

老人ホーム経営のようなヘルスケア不動産への投資は、超高齢社会が進むにつれて、より一層注目を集めている分野です。
しかし、老人ホーム経営に興味はあるものの「本当に儲かるのか」「どのくらい費用がかかるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、老人ホームの基礎知識や経営の収支構造を解説します。
民間事業者で多い老人ホーム経営の種類や、経営難を回避して成功を収めるコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
老人ホーム経営の基礎知識

ここでは老人ホーム経営の基礎知識として、以下の3つを解説します。
- 老人ホームとは
- 収支構造
- 経営に必要な資格
順に見ていきましょう。
老人ホームとは
老人ホームとは、高齢者が安心・安全に暮らすために提供される住まいと生活支援の場です。
主に、介護が必要な高齢者向けの「介護施設」と、自立・軽度介護者向けの「生活支援型施設」に分けられます。
運営主体によって「公的施設」と「民間施設」に大別され、それぞれ入居条件やサービス内容が異なります。
下表は、代表的な施設をピックアップしてまとめたものです。
| 名称 | 概要 | |
| 公的施設 | 特別養護老人ホーム(特養) | ・要介護3以上の方が対象 ・待機期間が長い場合あり |
| 介護老人保健施設(老健) | ・要介護1以上の方が対象 ・リハビリ重視の施設 ・医療機関との連携あり |
|
| 民間施設 | 有料老人ホーム | ・自立~要介護の方が対象※ ・入居一時金や月額利用料+介護報酬が収入源 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | ・主に自立〜要支援者向け ・バリアフリー賃貸住宅、安否確認・生活相談サービスのみ |
※介護付き・住宅型・健康型といった種類によって対象者に違いあり
公的施設の経営は原則として社会福祉法人運営または地方自治体のため、民間事業者が開業する施設としては有料老人ホームやサ高住が多くなっています。
収支構造
老人ホーム経営で押さえておきたい収支構造として、以下の2つを解説します。
これは、ゴールドトラストに限らず、一般的に老人ホーム経営に共通する収支構造です。
- 主な支出(初期費用など)
- 主な収入(介護報酬など)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
主な支出(初期費用など)
【初期費用(イニシャルコスト)】
| 概要 | 相場 | |
| 建設費 | 平屋であれば費用を抑えられるが定員を増やせない | 2億円以上(30名規模の場合) |
| 土地代 | エリアや地域によって異なる | 約1億円 |
| 設備・備品 | 家具や衛生用品等 | 約1,800万~3,200万円 |
| 採用費 | 入居者3人に対し1人の介護職員または看護職員を配置する基準あり | 約200万~300万円 |
| 販促・広告・営業費 | ネット広告やパンフレット作成費等 | 約200万~300万円 |
【維持費用(ランニングコスト)】
| 概要 | 相場 | |
| 人件費等 | 常勤スタッフ・看護師等の人件費 | 売上の40〜50% |
| 維持管理費 | 光熱費、固定資産税等 | 10万〜30万円/月 |
| 固定資産税 | 市区町村によって軽減措置あり | 土地建物の評価額の1.4% |
| 食費 | 介護保険施設における基準費用額に準ずる | 100万~130万円/月 |
老人ホーム経営には土地の取得費や建築費のほか、開業のためにかかる費用など多岐にわたる初期投資が発生します。
特に新築での開業を目指す場合は、施設の規模にもよりますが、約3.2億~5.2億円の資金が必要です。
また、開業後しばらくは赤字が続くことも珍しくないため、運転資金も含めた資金計画が欠かせません。
金融機関からの融資や補助金の活用も視野に入れ、無理のない資金調達プランが必要です。
老人ホーム経営で多い「サ高住」の建設費用や金銭的コストを抑えるコツについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】サ高住の建設費用はいくら?コスト削減のコツや業者の選定ポイントを解説
引用元:日本医療福祉建築協会|平成24年度良質な特別養護老人ホーム建設コスト低減手法に関する調査研究報告書
主な収入(介護報酬など)
| 項目 | 種類 | 概要 | 相場 |
| 入居一時金 | 一時金収入 | 入居時のまとまった収入源 | 0~数千万円 |
| 月額利用料 | 家賃・管理費・食費 など | 毎月の安定収入 | ・家賃10万〜30万円 ・管理費3万〜20万円 ・食費5万〜10万円 |
| 介護報酬 | 保険給付 | 要介護者の要介護度により異なる | 公定価格(※)で算定 |
| その他 | 保険外サービス | 通院同行費など任意 | 施設により異なる |
※介護にかかる報酬で、政府が決めた販売価格
運営の委託有無によって、主な収入が異なります。
運営を委託しない場合は、入居一時金+月額利用料+介護報酬が主な収入源です。
一方委託型では、家賃収入が中心です。
委託先がサービス運営をするため、人件費や介護報酬は受託者の負担となります。
経営に必要な資格
老人ホームの経営を始めるために、経営者自身が介護や福祉関連の資格を保有している必要はありません。
つまり、法人を設立すれば、介護施設の開業そのものは可能です。
ただし、介護保険サービスを提供して収益を得るには、都道府県や市区町村から「指定介護サービス事業者」としての認可を受ける必要があります。
この指定を取得するには、以下のように事業開始の数か月前から準備が必要です(東京都の例)。
- 開設予定月の4か月前に「新規指定前研修」の申込み
- 3か月前までに研修受講
- 2か月前の15日までに申請書提出
- 審査
- 指定取得
また、指定前研修には、事業所の管理者や法人代表予定者が参加する必要があり、研修申込み時点で事業内容が具体化する必要があります。
施設の種類によって資格要件が異なるケースもあるため、事前に管轄の行政庁へ確認すると良いでしょう。
老人ホームは儲かる?経営者の平均年収をチェック

老人ホームの経営者は、法人代表としての報酬を受け取りますが、公的データ上で直接の年収統計は存在しません。
そこで目安として、公的施設かつ運営も自分で行うパターンの平均年収について、管理職の平均給与をもとに概算を算出します。
経営者=管理者ではないため、あくまでも目安として参考にしてください。
例えば、特別養護老人ホームにおける管理者の平均月給は43万6,850円です。
12か月で計算すると、年収は約524万円となります。
代表的な3施設における管理者の平均年収などは、下表の通りです。
| 施設種別 | 平均年収 | 平均年齢 | 月の実労働時間 |
| 特別養護老人ホーム | 約524万円 | 45.3歳 | 165.2時間 |
| 介護老人保健施設 | 約504万円 | 45.8歳 | 160.9時間 |
| 特定施設入居者生活介護※ | 約485万円 | 45.9歳 | 166.2時間 |
※有料老人ホームや介護型のサ高住を含む
なお、これらはあくまで施設内管理職のデータであり、実際の経営者報酬は業績や法人規模などによって大きく異なる点に注意しましょう。
引用元:厚生労働省老健局老人保健課|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
【経営破綻が続出?】老人ホームの収益状況

老人ホームは高齢化社会の必需インフラである一方、安定した収益を上げることが難しい業種としても知られています。
特に近年は、経営悪化や赤字経営の施設が増加しつつあり、利益率や経営リスクが注目されています。
- 収支差率
- 経営難に陥りやすい理由
- 将来性
順に見ていきましょう。
収支差率(利益率)
老人ホームの収支差率(利益率)は下表の通り、おおむね低水準にとどまっています。
| 年度 | 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 特定施設生活介護※ |
| 令和2年度 | 1.2% | 2.1% | 4.4% |
| 令和3年度 | 1.2% | 1.5% | 3.9% |
| 令和4年度 | -1.0% | -1.1% | 2.9% |
※有料老人ホームや介護型のサ高住を含む
特養・老健は3割〜4割が赤字経営という、厳しい結果となっています。
なお、不動産投資とともに施設運営する形としては、障がい者グループホームも選択肢に入ってきます。
障がい者グループホームの経営状況と比較したい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
【関連記事】障がい者グループホームの経営は良好?実態やシミュレーション・落とし穴も
引用元:
・厚生労働省老健局老人保健課|令和5年度介護事業経営実態調査結果
・WAMNET|Research Report – 2023 年度特別養護老人ホームの経営状況について
経営難に陥りやすい理由
介護施設が経営難に陥る背景には、以下のような要因があります。
- 利益率が低いビジネスモデル
- 人材確保・定着が困難
- 競合の増加による利用者獲得競争
介護施設は、国の制度に基づく「公定価格(※)」で収入が決まる仕組みのため、自由な価格設定ができません。
※介護にかかる報酬で、政府が決めた販売価格
基本的な収入は介護報酬ですが、報酬改定のたびに収益構造が左右され、経営の安定性に欠ける点が大きな課題です。
加えて、慢性的な人手不足により採用・定着が難しく、十分なサービス提供が困難になる場合も少なくありません。
また、昨今では民間企業の参入も進み、競争の激化が顕著です。
サービスの質で差別化を図ろうとしても、過剰投資がコスト増に直結し、結果的に経営を圧迫するケースもあります。
このような複合的な要因が、介護施設を「儲かりにくく経営が難しい」といわれる背景となっています。
将来性
老人ホームや介護施設の需要は、今後も増加傾向が続くと予想されます。
日本は世界有数の超高齢社会に突入しており、今後も高齢者人口は確実に増加すると見込まれているためです。
実際、令和6年10月時点で65歳以上の人口は3,624万人にのぼり、総人口に占める割合は約3割にのぼっています。
介護保険総費用も右肩上がりで増えており、2025年度予算案では14.3兆円と過去最高額です。
一方で、施設数の増加だけでなく、重視されているのは次のような点です。
- サービスの質や効率的な運営
- ICTの活用
- 人材育成
供給過剰や競争激化を避けつつ、需要を的確に捉える経営戦略が求められるでしょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、高齢者のための住宅設計はもとより、介護事業の運営など、失敗しない「サ高住」運営のサポートを行っています。
老人ホーム経営を検討している方は、ぜひ一度「サービス付き高齢者向け住宅:ゴールドエイジ」をご覧ください。
引用元:
・内閣府|令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)
・シルバー新報|介護保険総費用は14.3兆円厚労省老健局25年度予算案
民間事業者で多い老人ホーム経営の種類

民間事業者で多い老人ホーム経営の種類を3つ紹介します。
- サ高住
- 有料老人ホーム
- 特養などの公的施設
それぞれ詳しく見ていきましょう。
種類①:サ高住
| 入居条件 | ・原則として60歳以上か、要介護・要支援認定を受けていることが条件だが、介護認定が必要ないケースも多い ・ただし施設によっては、自立生活が送れることや、感染症にかかっていないなど、独自の入居条件を設けている場合あり |
| 費用 | ・入居時にかかる費用相場:敷金(賃貸の場合)0~27万円 ・月額相場:11.1万~20万円 |
| 利用者数 | 27万8,320人 |
サ高住は介護施設ではなく、あくまで住宅として扱われる住まいです。
制度創設(2011年)以降、バリアフリー構造と安否確認・生活相談を組み合わせた住まいとして急増しています。
民間参入が容易で、比較的低資本で開業可能です。
施設規模を30戸以上にすれば収支安定性が向上し、戸数が多いほど損益分岐点を超えやすくなります。
自立〜軽度要介護利用者を中心に受け入れ、食事・清掃サービスも提供します。
運営上は夜間帯の安否対応などが中心で、介護付き有料老人ホームよりも、人件費負担が軽い点に強みがあるでしょう。
近年需要が高まっている「サ高住」の経営や投資に興味がある方は、ぜひ下記の記事もご覧ください。
【関連記事】不動産投資で「サ高住」がおすすめの理由|収支内訳や向いている人も解説
種類②:有料老人ホーム
| 入居条件 | ・施設の種類や運営する会社によって異なる ・一般的に考慮される項目 ・年齢 ・要介護度 ・医療依存度 ・身元引受人の有無 ・収入 など |
| 費用 | ・入居時にかかる費用相場:0~1,380万円 ・月額相場:8.8万~29.8万円 |
| 利用者数 | 61万1,056人 |
有料老人ホームの中でも、介護付きタイプは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けています。
施設内で介護を完結できる点が強みですが、人件費・設備投資は高くなりがちです。
また、民間企業が多く参入しており、競争は激化しています。
差別化には、独自の付加価値や医療連携などが求められ、経営には高度な戦略が必要です。
種類③:特養などの公的施設
| 入居条件 | ・特別養護老人ホーム:原則として65歳以上で要介護3以上 ・介護老人保健施設:原則として65歳以上で要介護1以上 |
| 費用 | ・入居時費用は不要 ・月額相場 ・特別養護老人ホーム:10万~14.4万円 ・介護老人保健施設:8.8万~15.1万円 |
| 利用者数 | ・特別養護老人ホーム:64万1,700人 ・介護老人保健施設:34万7,800人 |
特養や老健は、社会福祉法人や医療法人が運営する公的な施設です。
介護報酬や公的補助金を活用して運営されるため、利用者の費用負担が抑えられており、低所得者でも入居しやすい特徴があります。
近年では、不動産オーナーが土地や建物を用意し、社会福祉法人へ貸し出すかたちで運営を委ねるケースも増えています。
この方式なら法人側は初期投資を抑えつつ開業が可能で、不動産提供側も安定収益を得やすいでしょう。
老人ホームの経営難を回避して成功するコツ

老人ホーム経営は社会的意義が大きく、適切な戦略と専門家のサポートがあれば成功の可能性が高くなります。
ここでは、経営難を回避して成功するコツを3つ紹介します。
- 補助金や税制の優遇制度を有効活用する
- 黒字施設・赤字施設の違いを理解する
- サービスの質を向上させる
順に説明します。
コツ①:補助金や税制の優遇制度を有効活用する
老人ホーム経営を安定させるには、国や自治体が提供する補助金・税制優遇制度の積極的な活用が重要です。
特にサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、一定の基準を満たせば、建設費の補助や税制上の優遇が受けられる代表的な制度対象となっています。
例えば、一定の床面積やバリアフリー基準をクリアしたサ高住であれば、登録時に建設費の補助を受けられるほか、固定資産税の減免や不動産取得税の軽減措置が設けられています。
また、2027年(令和9年)3月まで特例措置が延長されており、今後の開業を検討している方にとっては好機といえるでしょう。
サ高住の開業・経営で適用される税制優遇制度の条件・期間などは、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】サ高住用物件の取得時に利用できる減免制度とは?金額・要件・手続きを解説
引用元:
・国土交通省|サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
・国土交通省|令和7年度税制改正概要
コツ②:黒字施設・赤字施設の違いを理解する
老人ホーム経営において、黒字と赤字の差を分ける最大の要因は「人件費率」と「稼働率(入所率)」です。
WAMの調査によると黒字施設の人件費率は平均49.4%、赤字施設は55.4%と、6ポイント以上の差が出ています。
赤字の一因として、職員数の過多や効率的なシフト設計の不備があります。
また、黒字施設では稼働率(入所率)が95%以上である一方、赤字施設では90%未満にとどまっており、空室が収益に直結している点も明らかです。
さらに、黒字施設ほど委託費や施設管理費などのコストを抑え、収入に対する支出のバランスが良好です。
経営を安定させるためには、下記のような経費と収益における構造の精査が求められます。
- 無理のない人員配置
- 空室を生まないマーケティング
- 外注費の見直し など
老人ホーム経営が成功しているケースでは単に入居者を集めているだけではなく、支出構造にも細やかに目を配っているといえるでしょう。
引用元:WAMNET|Research Report – 2023年度特別養護老人ホームの経営状況について
コツ③:サービスの質を向上させる
老人ホーム経営を成功させるには、サービスの質をいかに高めるかが重要です。
特に近年は、ICT(情報通信技術)を活用した職場環境の改善が注目されています。
例えば、介護記録の電子化や見守りシステムの導入は業務負担を軽減し、職員が利用者に向き合う時間の確保が可能です。
職員の業務が効率化されれば、離職率の低下や人材の定着にもつながり、長期的にはサービスの安定提供が実現します。
また、質の高いサービスは利用者満足度を高め、口コミや紹介による新規入居者の獲得にも好影響をもたらします。
加えて、厚生労働省や自治体ではICT導入に対する補助制度も整備されており、これらを活用すれば費用面の負担を抑えながら改善が図れるでしょう。
このように、業務の効率化とサービスの質の両立が経営安定の基盤を築くポイントとなります。
老人ホーム経営に挑戦したい方はゴールドトラストへ

老人ホーム経営は社会貢献性の高いビジネスである一方、初期投資や制度の理解など多様なノウハウが求められる高度な事業です。
そこでおすすめしたいのが、弊社ゴールドトラストが提供する「100億円資産形成倶楽部」です。
富裕層や資産家の方々を対象に、老人ホーム経営を通じた安定的な資産形成を支援します。
事業計画の立案から資金調達、開業・運営までワンストップでサポートが受けられます。
さらに、入会者限定で優良条件の土地紹介も実施しており、事業の立ち上げにおける最大の壁をクリアできます。
自社ブランドの「サービス付き高齢者向け住宅:ゴールドエイジ」での建設支援も行っており、サ高住経営に特化したノウハウと実績が強みです。
老人ホーム経営の未経験者でも安心して取り組める体制が整っているため、新たな収益基盤を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:老人ホーム経営を成功させるためには相応のノウハウが必要

老人ホーム経営は高齢化が進む日本において将来性あるビジネスですが、初期費用の大きさや人材確保などの課題も多く、成功には的確な戦略と専門的な知識が欠かせません。
そこで注目されるのが、事業計画から運営支援まで一貫してサポートする「100億円資産形成倶楽部」です。
「将来のために資産形成もしたい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】サ高住経営で失敗する要因とその対策方法をわかりやすく解説
【関連記事】サ高住経営は儲かる?メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説
【関連記事】【早見表付き】遺産1億円の相続税はいくら?計算方法や節税対策も解説