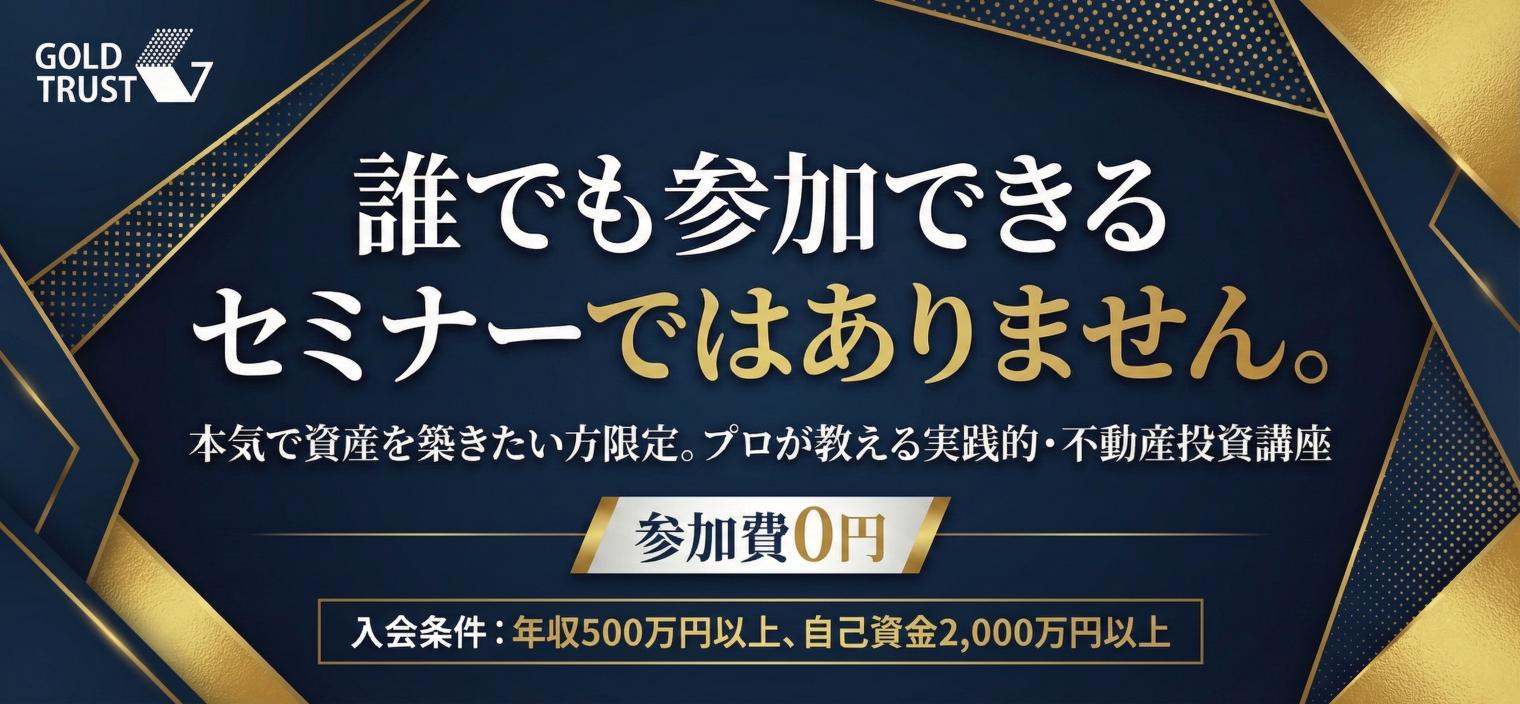サ高住用物件の取得時に利用できる減免制度とは?金額・要件・手続きを解説

高齢化が社会問題となっている日本では、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の需要が高まっています。
取得の際には減免制度が利用できるなど、投資先としても注目されている不動産のひとつ です。
しかし、「サ高住用物件における減免制度の内容や要件が分からず、投資をするには至っていない」という方もいるでしょう。
この記事ではサ高住用物件の取得時に利用できる減免制度について、金額・要件・手続きとともに解説します。
サ高住物件の建設時に利用できる補助金・融資制度もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
サ高住投資とは

そもそもサ高住とは、高齢者向けの住宅のことです
バリアフリー構造になっており、安否確認・生活相談サービスが受けられます。
高齢化が進む日本では、今後ますます需要が高まると予想され、不動産投資においても注目の物件です。
不動産投資としてサ高住を選ぶメリットは、以下の5つが挙げられます。
- 空室のリスクが少ない
- 立地条件に左右されない
- 家賃収入だけでなく介護サービスでの収益も見込める
- 減免制度が利用できる
- 補助金・融資制度が利用できる
市場が拡大傾向にあり、立地の影響を受けない点は大きなメリットです。
減免制度や補助金・融資制度の詳細に関しては次項以降で解説しているので、あわせてチェックしてください。
なお、サ高住投資の収支内訳や向いている人について知りたい方は、下記の記事も参照しましょう。
【関連記事】不動産投資で「サ高住」がおすすめの理由|収支内訳や向いている人も解説
サ高住用物件の取得時に利用できる減免制度

サ高住用物件の取得時には、以下に挙げる2つの税金に対して減免制度が利用できます。
- 固定資産税
- 不動産取得税
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、サ高住の取得から運営までをサポートする「サービス付き高齢者向け住宅:ゴールドエイジ」を提供しています。
サ高住用物件の取得を検討している方は、ぜひ一度お問い合わせください。
減免対象①:固定資産税
固定資産税に対する減免制度について、以下に挙げる3点をもとに解説します。
- 減額内容
- 要件
- 手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
減額内容
固定資産税における減免制度の減額内容は、下表の通りです。
| 減額の金額 | 1戸あたり120㎡(36.3坪)までの居住部分に対して、3分の2を基準として減額 (2分の1〜6分の5の範囲内において市町村の条例で定める割合) |
| 減額される期間 | 新築から5年間 |
減額の金額は基準が定められているものの、市町村により異なります。
居住者が立ち入らない事務所や更衣室などは、減額の対象となりません。
ただし、他の減額措置と重複して利用できない点には注意しましょう。
要件
固定資産税における減免制度の要件は、下表の通りです。
| 床面積 | 30㎡(9.07坪)以上180㎡(54.45坪)以下/戸であること※ |
| 戸数 | 10戸以上であること |
| 補助 | 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること |
| 構造 | 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること など |
※共用部分含み、一般新築特例は40㎡(12.1坪)以上280㎡(84.7坪)以下/戸
適用期限は延長されており、2027年3月31日までとなっています。
サ高住用物件を取得する際には、要件に沿っているか必ず確認しましょう。
手続き
減免制度の利用には、市町村ごとに用意されている「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」による申請が必要です。
申請時には、以下に挙げる書類もあわせて提出します。
- 都道府県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることを証する書類の写し
- 国から建設費の補助を受けていることを証する書類の写し
- 各階平面図の写し など
市町村によって必要書類は異なるため、確認のうえ用意してください。
基本的には新築した年の翌年1月31日までの申請となり、過ぎていると理由の記載も求められます。
期限に間に合うよう必要書類を準備し、忘れず申請しましょう。
減免対象②:不動産取得税
続いて、不動産取得税に対する減免制度について、以下に挙げる3点をもとに解説します。
- 減額内容
- 要件
- 手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
減額内容
不動産取得税における減額内容は、家屋および土地で異なり、それぞれ下表の通りです。
| 家屋 | 課税標準から1,200万円/戸を控除 |
| 土地 | 課税標準から以下のいずれか大きい金額を控除 ・4万5,000円(150万円×税率3%) ・土地の評価額×1/2(特例負担調整措置)×家屋の床面積の2倍※×税率3% |
※200㎡(60.5坪)を限度
なお、サ高住用物件を介護事業者などへ貸し出すと、相続税対策にもなります。
貸家扱いにでき、相続財産の評価額が減少するためです。
遺産1億円の場合における相続税の基礎知識や節税対策について知りたい方は、下記の記事もご参照ください。
【関連記事】【早見表付き】遺産1億円の相続税はいくら?計算方法や節税対策も解説
要件
不動産取得税における減免制度の要件は、下表の通りです。
| 床面積 | 30㎡(9.07坪)以上180㎡(54.45坪)以下/戸であること※ |
| 戸数 | 10戸以上であること |
| 補助 | 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること |
| 構造 | 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること など |
※共用部分含み、一般新築特例は40㎡(12.1坪)以上280㎡(84.7坪)以下/戸
固定資産税・不動産取得税ともに、減免制度の要件は共通しています。
いずれの申請にも対応できるよう、要件を満たしているか確認しましょう。
手続き
不動産取得税における減免制度の利用には、以下に挙げる書類を準備のうえ、自治体に申請します。
- 不動産取得税減額申請書兼還付申請書
- 住宅の登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書
- 国から建設費の補助を受けていることを証する書類の写し
- 各階平面図の写し など
上記はあくまで一例であり、自治体ごとに必要となる書類は異なります。
申請する際には、各自治体に確認してから手続きを進めましょう。
サ高住の減免制度が不動産投資に与える影響

サ高住の減免制度を利用すると、初期コストはもちろん、継続的な運用コストの圧縮につながり、資金繰りがしやすくなります。
結果として、建設・開業後も経営が早期に安定しやすくなり、収益確保もスムーズに進むなど、減免制度を利用する大きなメリットです。
比較的コストがかかるサ高住の不動産投資において、減免の有無は大きな差となり得ます。
サ高住事業を成功に導くためには、減免制度の有効活用が不可欠であるといえるでしょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
サ高住経営のメリット・デメリットや注意点について知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしましょう。
【関連記事】サ高住経営は儲かる?メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説
【減免以外も】サ高住の建設時に利用できる補助金・融資制度

サ高住の建設時に利用できる補助金・融資制度は、以下に挙げる2つです。
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
それぞれ詳しく見ていきましょう。
サ高住の建設費用やコスト削減のコツについて知りたい方は、下記の記事もぜひチェックしてください。
【関連記事】サ高住の建設費用はいくら?コスト削減のコツや業者の選定ポイントを解説
制度①:サービス付き高齢者向け住宅整備事業
スマートウェルネス住宅等推進事業に含まれる「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」について、以下の3つを踏まえて紹介します。
- 補助内容
- 要件
- 手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
補助内容
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助内容は、下表の通りです。
| 補助率 | 補助対象・限度額 | ||
| 新築 | 床面積30㎡(9.07坪)以上
(かつ一定の設備完備) |
1/10 | 135万円/戸 |
| 床面積25㎡(7.56坪)以上 | 120万円/戸
(住棟の全住戸数の2割を上限に適用) |
||
| 床面積25㎡(7.56坪)未満 | 70万円/戸 | ||
| 改修 | 1/3 | 195万円/戸 | |
| 既設改修 | 1/3 | 10万円/戸
(既設サ高住のIoT導入に対する補助) |
|
ただし、事業目的の達成に必要な範囲を逸脱する華美または過大な設備は、補助対象外です。
また、改修においては、共用部分やバリアフリー化に係る工事などに限られます。
新築や改修によって、補助率および限度額は異なると認識しましょう。
要件
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の要件は、以下の通りです。
- 高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること
- 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額(11.2~25.6万円/月)とすること
- 入居者の家賃が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと
- 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること
- 情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと
- 新築・改修の場合は、都道府県や市区町村のまちづくり方針と整合していること
- 事業主体が運営する介護保険法に基づく指定事業所が指定取消等の対象である場合に、当該事業主体の組織的な関与があったことが認められないこと など
市街化調整区域や土砂災害警戒区域・浸水想定区域は補助の対象外とされています。
前提としてサ高住の役割を、正しく果たせているかという点に留意しましょう。
手続き
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助に申請する手順は、以下の6ステップです。
- サ高住の登録窓口に登録申請
- 整備事業事務局に交付申請書の提出
- 交付決定通知の発出
- 事業着手
- 完了実績報告の提出
- 補助金額の確定・支払い
補助の申請前に、まずサ高住の登録が必要です。
補助金の受領後も定期的な運営状況等の報告が求められ、事務局による内容の審査が行われます。
スムーズに進められるよう、流れを把握して申請に取りかかりましょう。
制度②:サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
続いて「サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資」について、以下の3つを踏まえながら紹介します。
- 融資内容
- 要件
- 手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
融資内容
サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資の内容は、下表の通りです。
| 融資額 | 融資対象事業費の100%以内(10万円以上、10万円単位) |
| 返済期間 | 35年以内(1年単位) |
| 融資金利 | 以下の4タイプから選択 ・35年固定金利(繰上返済制限あり) ・35年固定金利(繰上返済制限なし) ・15年固定金利(繰上返済制限あり) ・15年固定金利(繰上返済制限なし) (一般住宅型・施設共用型のそれぞれで金利は異なります) |
| 返済方法 | 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い |
| 担保 | 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定 |
融資金利のタイプは申し込み後に変更できないため、注意が必要です。
また、融資金利は毎月見直されるので、住宅金融支援機構より最新情報をご確認ください。
要件
融資対象となる賃貸住宅の主な要件は、以下の通りです。
- 「サービス付き高齢者向け住宅」としての登録を受ける賃貸住宅であること(返済期間中は、5年ごとの登録更新を行うこと)
- 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上または建築物エネルギー消費性能基準のいずれかの性能を満たすこと
- 融資対象となる賃貸住宅部分の延べ面積が200㎡(60.5坪)以上であること
- 敷地面積が165㎡(49.91坪)以上であること
- その他機構が定める技術基準に適合すること
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていること
土砂災害特別警戒区域内および浸水被害防止区域内は対象外となります。
また、融資対象者における主な要件は、以下の通りです。
- 返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
- 個人で年齢が満65歳以上の場合、満65歳未満の後継者と連名により申し込める方
- 法人の場合、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名により申し込める方
- 建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)を持っている方(取得予定の方を含む)
- 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人の連帯保証人をつけられる方(一般住宅型の場合)
- 個人(日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方)または法人
連帯保証人には、機構が承認している保証機関も利用可能です。
なお、審査の結果、融資を受けられない場合や希望額から減額される場合もあります。
審査を通過するためにも、事前に各要件をチェックしておきましょう。
手続き
融資の申し込み先となるのは、機構窓口である本店事業融資部サ高住グループです。
融資手続きは、以下の流れで進行します。
- 事前審査・融資の申し込み
- 融資審査
- 融資内容の決定
- 設計検査
- 着工
- 入居者の募集
- 融資基本約定書の提出・中間資金の受取
- 竣工
- 竣工現場検査・工事費精算報告
- 融資額の確定
- 契約
- 最終回資金の受取
原則として、申し込みから2年経過するまでに、着工する必要があります。
最終的に融資を受けるまで多くの手順を要しますが、ひとつひとつ着実に進めていきましょう。
サ高住の減免制度を有効活用した開業方法

ここでは、サ高住の減免制度を有効活用した開業方法として、以下の2つを紹介します。
- 開業までの流れ
- 要チェックポイント一覧
それぞれ詳しく見ていきましょう。
開業までの流れ
サ高住における減免制度を利用した、開業までの流れは以下の5ステップです。
- 事業計画・資金計画の策定
- 用地選定・建築計画
- 各種申請・認可手続き
- 施設建設・設備準備
- 人材確保・運営準備
まずは、必要経費や家賃収入などを踏まえた事業計画および、資金調達に向けた計画の策定からはじめます。
上述したサ高住の登録はもちろん、消防法関連の申請など、各種手続きはもれなく必要です。
施設・設備の準備は、補助金・融資制度の要件を満たすよう、注意して進めてください。
管理者やスタッフを確保して運営準備に入り、入居者が集まれば、開業となります。
安定した運営を目指すには、綿密な計画をはじめとする事前準備が重要です。
要チェックポイント一覧
減免制度の利用を前提にした、サ高住の取得および建設時に押さえるべき、構造上のポイントは下表の3つです。
| 床面積 | 30㎡(9.07坪)以上180㎡(54.45坪)以下/戸 |
| 戸数 | 10戸以上 |
| 耐火性能 | 主要構造部が耐火構造または準耐火構造 |
以上は、補助金・融資制度のいずれにも共通するため、必ずチェックしましょう。
減免制度を使ってサ高住投資を成功させたい方は

サ高住投資を成功させるには、減免制度の有効活用が重要なポイントです。
初期コストを抑制でき、早期安定にもつながります。
ただし、補助金・融資制度を利用するには、それぞれ定められた要件に準拠する必要があります。
複雑な制度理解と活用には専門知識を有するため、サ高住投資に踏み切るのはハードルが高いのも実情です。
なお、弊社が運営する「100億円資産形成倶楽部」では、富裕層の多角的な資産形成の一環として、サ高住投資の包括的なサポートを提供しています。
現在、100億円資産形成倶楽部へ入会いただいた方には、優良条件の土地も紹介中です。
あわせて「サービス付き高齢者向け住宅:ゴールドエイジ」では、サ高住の建設も支援しているので、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
まとめ:サ高住投資をするなら減免制度の活用が必須

サ高住投資をするなら、減免制度および補助金・融資の活用が必要不可欠です。
各制度をうまく利用し、サ高住の安定した運営に結びつけましょう。
なお、弊社ゴールドトラストが運営する「100億円資産形成倶楽部」では、資産形成を実現するためのノウハウをお伝えしています。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】日本の不動産価格は今後下がる?都道府県別の推移とともに見通しも解説
【関連記事】不動産投資の失敗率は高い?主な資産運用との比較や要因・成功させるコツも
【関連記事】不動産投資ローンの金利ランキング!相場や返済額のシミュレーションも解説