退職金のおすすめ運用方法5選|安全に資産を増やす・守るポイントも解説

現代は、「定年退職後に生活を続けるためには、2,000万円が必要」と言われています。
しかし、「退職金だけでは足りない」「老後に備えてお金を増やしたいけれど、どうしたら良いか分からない」という方も多いでしょう。
この記事では、退職金のおすすめ運用方法を解説します。
運用時のメリットや注意点のほか、失敗例や相談先もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
目次
【老後2000万問題に備えて】退職金のおすすめ運用方法5選

老後2000万問題とは、「定年退職後の生活に必要な資金が30年で2,000万円にのぼる」と言われているものです。
2019年6月に金融庁が発表した、「高齢社会における資産形成・管理」という報告書がきっかけで話題となりました。
平均寿命の延びや退職金の減少などの理由から、退職金や公的年金だけで生活していくのは難しいと推測されています。
ここでは、老後2000万問題に備えるための効果的な退職金の運用方法を5つ紹介します。
- 退職金定期預金
- 貯蓄型保険
- 不動産投資
- 株式会社投資
- 個人向け国債
老後2000万円問題に備えた資金シミュレーションや解決策について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】老後2,000万円問題とは?シミュレーションをもとに今できる解決策も解説 | 資産形成ブログ
引用元:金融庁|金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書[高齢社会における資産形成・管理」
運用方法①:退職金定期預金
| メリット | デメリット |
| ・普通預金や定期預金に比べ金利が高い ・元本が保証される |
・高金利の適用期間が短い ・金融機関によっては、投資信託などとセットの利用が求められる |
退職金定期預金は預け入れる資金を退職金に限定した金融商品で、通常の定期預金よりも高い金利が魅力です。
ただし、高金利が適用される期間が3か月などと限られており、適用期間が過ぎると通常の預金に切り替える方法が主流です。
そのため、高金利が適用された後の別の運用方法を考えておくことをおすすめします。
さらに、退職金定期預金はどの金融機関でも扱っているわけではありません。
ご自身が普段利用している銀行などで扱っていない可能性もあるため、事前に確認しましょう。
運用方法②:貯蓄型保険
| メリット | デメリット |
| ・保険料が掛け捨てにならない ・解約時に返戻金が受け取れる |
・掛け捨て型の保険に比べ保険料が高い ・解約した場合元本割れのリスクがある |
貯蓄性が高い貯蓄型保険には、終身保険や養老保険などがあります。
貯蓄型の保険であれば解約返戻金が受け取れることに加え、場合によっては支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れることもメリットです。
また、生命保険控除の対象になるため、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。
貯蓄型保険は、万が一に備えながら積み立てもしたい方におすすめです。
運用方法③:不動産投資
| メリット | デメリット |
| ・キャピタルゲインが見込める ・安定したインカムゲインが見込める |
・初期費用が高い ・物件選びが難しい ・運用するために専門知識が必要 |
不動産投資では所有したマンションやアパートから家賃収入(インカムゲイン)を得ることで、安定した不労所得が得られます。
不動産はインフレに強く、物価が上昇した際には売却によって大きな利益(キャピタルゲイン)を得ることも可能です。
ただし、投資に不利な物件を購入すれば、大幅修繕や空室など多くのリスクを背負いかねません。
弊社ゴールドトラストでは、土地がセットになって初心者でも収益を得やすい「賃貸マンションアパート(一棟買い):トチプラス」を展開しております。
プロの支援を受けながら不動産投資を始めてみたい方は、ぜひ一度ご覧ください。
また、不動産投資のリスクに不安を感じる方には、投資信託による運用がおすすめです。
不動産投資信託(REIT)の仕組みやメリットについての知識を得たい方は、以下の記事もあわせてチェックしましょう。
【関連記事】不動産投資信託(REIT)とは?メリット・デメリットや利回りを解説
運用方法④:株式投資
| メリット | デメリット |
| ・売却益や配当金を得られる ・株主優待を受けられる場合がある |
・元本割れのリスクがある |
株式投資の魅力は、売却益や配当金に加え株主優待があることです。
企業によっては、下記のようなさまざまな株主優待を提供しているところもあります。
- 自社製品
- カタログギフト
- 商品券やクオカード
さらに、小額投資から始められる点も魅力です。
最低投資額が100万円を超える一部の銘柄もありますが、10万円以下で投資できる銘柄も多く安心です。
今後の成長が期待される、あるいは業績が安定している企業のうち、高配当を行っている銘柄を選んで購入すれば、保有株数に応じた配当金が受け取れます。
不動産投資と株式投資それぞれの基礎知識やメリット・デメリットについて知りたい方は、下記の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】不動産と株はどっちがおすすめ?利回りや運用のしやすさなど5項目で比較
運用方法⑤:個人向け国債
| メリット | デメリット |
| ・中途解約ができる ・購入は1万円から可能 |
・大きなリターンは見込めない |
国債は、国が資金調達のために発行する債券です。
購入の際に利率と満期が決まっており、満期まで保有すれば元本と利息が受け取れます。
中途解約は可能ですが、受け取れる利息が少なくなる点には注意が必要です。
とはいえ、国の借金ということで破綻するリスクが低いことから、大きなリターンは見込めない代わりに、安全性を重視する人に向いています。
退職金を資産運用に回す3つのメリット

退職金を資産運用に回すメリットは、以下の3つです。
- 新たな収入源になる
- 貯金が尽きるタイミングを遅らせられる
- インフレ対策として期待できる
順に見ていきましょう。
メリット①:新たな収入源になる
退職金を資産運用に回せば、新たな収入源を確保できます。
定年退職後は、収入が途絶える人も少なくありません。
再雇用やパートで働く方もいますが、現役の頃と比べると多くの方が大幅に収入減となります。
また、今は働いている方でも、今後年齢を重ねるごとに働いて収入を得ることが難しくなってきます。
退職金を資産運用に回すことで資産を増やせれば、労働以外の新たな収入源になり、安心して老後を迎えられるでしょう。
資産運用の基礎知識を身に付けるためのセミナーについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】【将来に備えて】資産運用セミナーに参加するメリットとは?注意点も解説
メリット②:貯金が尽きるタイミングを遅らせられる
貯金が尽きるタイミングを遅らせられることも、退職金を資産運用に回すメリットです。
現代では男女ともに平均寿命が大幅に延びており、定年退職後の人生は長くなっています。
実際、男性の平均寿命は81.05歳、女性の平均寿命は87.09歳となっており、定年を65歳とすると退職後の人生は20年近く続きます。
公的年金だけでは不足する生活費を補い、少しでも長く貯金を長持ちさせたい場合は、退職金の運用が有効な手段の1つとなるでしょう。
引用元
・厚生労働省|令和4年簡易生命表の概況
・厚生労働省|平均寿命の推移
メリット③:インフレ対策として期待できる
退職金を資産運用に回すことは、インフレ対策としても期待ができます。
インフレによりモノやサービスの価値が上がると、代価であるお金の価値が下がります。
例えば、今手元に2,000万円があったとしましょう。
20年後に、インフレでモノやサービスの価値が倍に上がったとすると、2,000万円が手元に残っていたとしても、1,000万円の価値しかなくなるのです。
そのため、今後もインフレが続くことを想定し、対策を立てておくことが重要です。
お金の価値が下がっても資産運用を続けて少しずつ増やすことで、将来的なインフレ対策としても有効になります。
【安全第一】退職金を資産運用に回す際の注意点
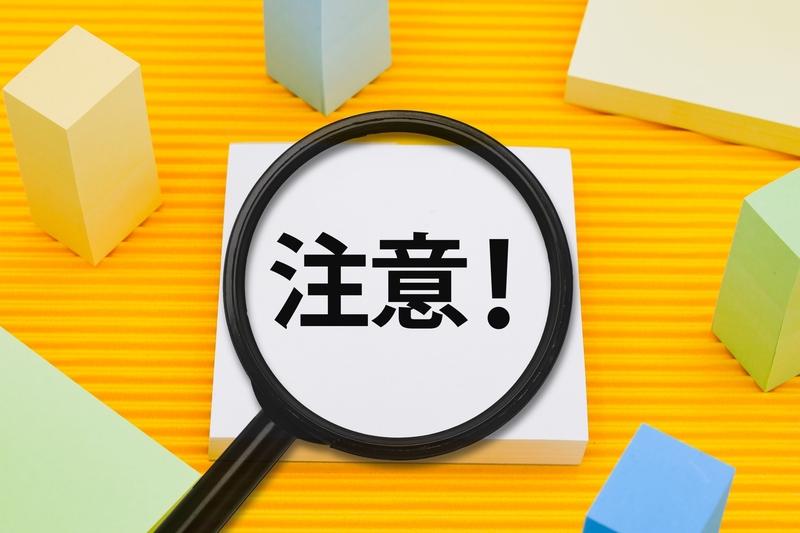
退職金を資産運用に回す際の注意点は、以下の2点です。
- 短期での成果は目指さない
- 分散・積立を意識する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
注意点①:短期での成果は目指さない
株式投資や投資信託など、価格が常に変動するもので運用する場合は、短期勝負の運用は避けましょう。
例えば、1年や3年などの短期運用では、たまたま価格が下がったところで終了してしまう可能性もあります。
仮に価格が下がったとしても、後々に回復を待てるよう長期の運用期間を持つことが必要です。
注意点②:分散・積立を意識する
退職金の資産運用でも、分散・積立を意識しましょう。
下表の例にあるとおり、重視する点が異なればポートフォリオ(※)も変わってきます。
※保有する資産の配分割合
| 資産を守る | 中間 | 資産を増やす | |
| 国内債券 | 80% | 55% | 25% |
| 外国債券 | 20% | 15% | 25% |
| 国内株式 | — | 20% | 25% |
| 外国株式 | — | 20% | 25% |
「資産を守る」ことを重視する場合は、100%債券で構成します。
「中間」のポートフォリオは債権が70%を占めており、運用リスクが低い一方で、株式によりある程度のリターンが期待できます。
4つの資産をそれぞれ25%ずつ組み入れているポートフォリオは、「資産を増やす」を重視するパターンです。
資産運用の目的に応じてポートフォリオを組み、適宜見直していきましょう。
退職金の運用でよくある失敗談

退職金の運用でよくある失敗談は、以下の3つです。
- すすめられるままよく確認せずに投資してしまう
- 資金の大半を投資にあててしまう
- 資産運用の目的があいまいなまま投資してしまう
金融機関からすすめられた商品をよく確認しないまま購入し、失敗するケースは少なくありません。
値動き時の対処が分からなかったり、途中解約が難しい商品に手を出してしまって損失を出したりするパターンです。
許容範囲を超える資金の投資によって、生活が困窮してしまう方もいます。
また、資産運用の目的を決めずに投資を始め資産を減らしてしまう失敗例もあります。
資産運用の知識を身に付けつつ、「何のために、いつまでにお金を作るのか」など具体的な目標を決めてから投資を始めるようにしましょう。
退職金の運用について相談できる場所

退職金の運用についてアドバイスしてもらえる相談先は、以下の5つです。
- 銀行
- 証券会社
- 保険会社
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
それぞれの特徴やサポート内容を見ていきましょう。
相談先①:銀行
銀行は、退職金の運用について気軽に相談できます。
銀行によっては、退職金の運用についての専門相談窓口もあります。
ただし、取り扱っている金融商品の数は証券会社に比べて少ないため、選択肢を銀行1本に絞らず、いくつか相談して比較検討することをおすすめします。
転勤などにより定期的に担当者が変わることや、担当者によって知識量が変わることも頭に入れておきましょう。
相談先②:証券会社
証券会社では、下記のようにさまざまな金融商品の相談が可能です。
- 株式投資信託
- 退職金定期預金
- 個人向け国債
- 株式投資
証券会社は、社員が金融商品や金融市場に関する深い知識を持っています。
資産運用の経験が少なく、運用の仕方が分からないという方も専門的なアドバイスが受けられます。
ただし、担当者が定期的に変わることや、担当者により知識量に違いがある点は銀行と同じです。
また、営業ノルマや企業利益を追求する必要性から、すすめられた商品がご自身に合っているとは限らない場合もあります。
相談する際には、すすめられた商品をそのまま購入せずに、本当にご自身の投資目的に沿っているか、許容範囲のコスト内かなどをチェックしましょう。
相談先③:保険会社
保険会社では、目的に応じたいろいろな保険商品の案内をしてもらえます。
その人の状況に応じた、保険金の受取シミュレーションを受けることも可能です。
保証と貯蓄を両立できる貯蓄型保険の説明や、相続税対策として活用できるメリットなどについてのアドバイスも受けられるでしょう。
相談先④:ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー(FP)には、家計管理やライフプランに関しての相談が可能です。
銀行や証券会社に勤務するFP保有者は自社の製品案内をしますが、通常、個別の金融商品の提案などは行いません。
家計の総合的な状況を見てもらい、全般的な資産運用のアドバイスを得ましょう。
相談先⑤:独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor)は、金融機関から独立した立場で顧客の資産運用をサポートする専門家です。
ファイナンシャルプランナーとよく混同されがちですが、具体的な投資のアドバイスや金融商品の紹介をする点に違いがあります。
証券会社などに属していないため、転勤により担当者が変わることもありません。
また、中立的な立場にあるため、金融会社から販売方針を指示されることもなく、その人に合った最適な商品の提案や仲介をしてもらえる点が強みです。
まとめ:退職金を資産運用に回すのも老後資金の確保に有効

安心して豊かな老後の生活を送るためには、お金の不安をなくして安定した生活基盤を築く必要があります。
老後資金の確保には、退職金の資産運用も有効な手段の1つです。
資産運用を始めたい方は、ご自身のライフプランに合った投資先を慎重に検討してみてください。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】【貯金3000万円の方向け】おすすめの投資方法5選!成功するコツも解説
【関連記事】【初心者向け】分散投資の種類とは?組み合わせるメリットや注意点も解説
【関連記事】インフレ対策に向いている投資法5選!上手に資産を守る・増やす方法も解説





