金融所得課税の引き上げはいつから?強化の影響や今からできる対策も解説

金融所得課税とは、株式などの金融商品から得た所得にかかる税金のことです。
投資に取り組むなかで、「金融所得課税の引き上げはいつから?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
金融所得課税の引き上げ時期を把握しないまま投資を続けると、税金の負担が重くなり、思ったような利益を得られない可能性があるため注意が必要です。
この記事では、金融所得課税の特徴や引き上げ時期を解説します。
金融所得課税の引き上げによる影響が大きい人・小さい人や備える方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
金融所得課税とは

金融所得課税とは、金融商品から得た所得にかかる税金のことです。
ここでは、以下の3点から金融所得課税について解説します。
- 課税の対象
- 課税方式
- 累進課税制度との違い
金融所得課税の引き上げ時期をチェックする前に、基礎知識について理解を深めましょう。
金融資産の特徴や純金融資産との違いが気になる方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】金融資産とは?純金融資産との違いや種類・日本人の保有額をわかりやすく解説
課税の対象
金融所得課税の対象は、以下の通りです。
- 投資信託
- 株式
- 預貯金 など
株式であれば配当金や譲渡の利益に対して、預金であれば利子に対して金融所得課税が発生します。
また、金融所得課税の税率は20.315%で、内訳は下表の通りです。
| 種類 | 税率 |
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
例えば、株式の配当金が10万円であった場合には、2万315円を税金として納める必要があります。
なお、新NISAやiDeCoも金融所得に分類されますが、これらの運用益には課税されない点を覚えておくと良いでしょう。
課税方式
金融所得課税の課税方式には、下表の3種類があります。
| 分類 | 種類 | 内容 |
| 総合課税 | 他の所得と合算して所得税を計算し、確定申告で納税する | |
| 分離課税 | 申告分離課税 | 他の所得と分けて税金を計算し、確定申告で納税する |
| 源泉分離課税 | 利息を受け取る際に他の所得と分けて源泉徴収される | |
分離課税に該当する「源泉分離課税」では、自動的に税金が差し引かれているため、基本的に確定申告は不要です。
加えて、申告分離課税を選択する場合にも、金融機関に開設した口座が「源泉徴収ありの特定口座」であれば、確定申告は原則必要ありません。
なお、預貯金の利子は所得税が源泉徴収される「源泉分離課税」が採用されています。
一方で、株式の配当金は基本として確定申告が求められますが、上場株式などの場合は申告分離課税を選ぶことも可能です。
このように、金融所得の種類によって課税方式が限定され得る点に注意しましょう。
引用元:国税庁|株式・配当・利子と税
累進課税制度との違い
金融所得課税と累進課税制度は下表のように、税率が異なります。
| 課税される所得金額 | 所得税 | 金融所得にかかる税率 |
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 20.315% |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | |
| 4,000万円以上 | 45% |
累進課税制度を適用している「所得税」の税率は5〜45%の7段階に設定されているのに対して、金融所得課税は所得金額に関係なく一律で20.315%です。
また、金融所得にかかる税金には住民税が含まれているものの、所得税には住民税の税率である10%が加算されます。
金融所得にかかる税率は基本的に20.315%ですが、株式の配当金は総合課税方式を選ぶと、累進課税が適用されるので注意しましょう。
引用元:国税庁|所得税の税率
金融所得課税はいつから引き上げられる?

金融所得課税の引き上げは、2025年1月1日以降の所得について適用されます。
具体的には、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、超えた部分に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超えると、超えた金額に相当する所得税が上乗せされる仕組みです。
基準所得金額とは、年間の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額を指し、金融所得も含まれます。
金融所得課税の引き上げは「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」として、2023年度の税制改正に盛り込まれ、本格的にスタートしました。
なお、金融所得課税の引き上げは「ミニマムタックス」や「富裕層ミニマム税」と呼ばれるケースがあります。
ミニマムタックスの特徴や影響を受ける・受けない人の違いについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】【2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い
金融所得課税が引き上げとなった背景
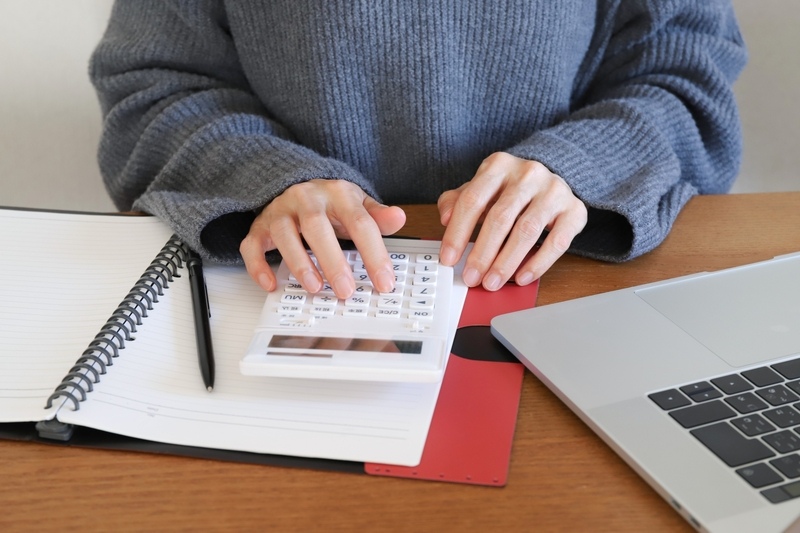
金融所得課税が引き上げとなった背景には、以下の3点があります。
- 「1億円の壁」問題の解決を図るため
- 社会保障給付費を確保したいため
- 海外と足並みをそろえるため
国内における金融所得課税の変遷や海外との比較について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】金融所得課税とは?日本と海外を比較!最新の動きや引き上げのリスクも解説
背景①:「1億円の壁」問題の解決を図るため
金融所得課税の引き上げには、「1億円の壁」問題の解決につなげる目的があります。
1億円の壁とは、所得額が年1億円を超えると所得税の実効税率が下がることです。
富裕層が株式の配当金などの金融所得を多く得ているなかで、税率が総合課税の所得税率よりも低いために1億円の壁の問題が発生しています。
2022年に発表された財務省の資料をもとに、2019年時における申告納税者の所得税負担率をチェックしましょう。
| 合計所得金額 | 所得税負担率 |
| 3,000万円 | 22.2% |
| 5,000万円 | 26.0% |
| 1億円 | 27.9% |
| 2億円 | 27.5% |
| 5億円 | 24.2% |
所得税負担率は、1億円をピークに徐々に下がっていくことが分かります。
なお、所得税負担率は合計所得金額が100億で下がり止まって、その場合の所得税負担率は16.1%です。
年度によって違いはあるものの、1億円を境界線にして所得税負担率は下がる傾向にあります。
税制改正前の金融所得課税は、富裕層に有利な仕組みと問題視されていました。
2025年より開始する金融所得課税の引き上げによって、税負担の公平性を高め、所得格差の是正が期待されています。
背景②:社会保障給付費を確保したいため
金融所得課税の引き上げの背景には、「社会保障給付費の確保」という面もあります。
日本は少子高齢化にともない、下表のように社会保障給付費が増加しており、財源の確保が急務です。
| 年 | 社会保障給付費の総額 |
| 2000 | 78.4兆円 |
| 2010 | 105.4兆円 |
| 2022 | 131.1兆円(予算ベース) |
社会保障給付費は増加傾向にあり、2000〜2022年の間に1.7倍程度にまで増加していることが分かります。
また、社会保障給付費における財源の構成は、年度によって異なるものの、保険料が約6割、税金が約4割です。
社会保障給付費の財源で半数以上を占める保険料は、総所得金額や給与所得を基準に算出されています。
金融所得を得ている場合、下表のように保険料に反映されないケースがあり、財源確保の点から課題とされていました。
| 種類 | 確定申告の有無 | 内容 |
| 国民健康保険 | あり | 社会保険料に反映される |
| なし | 社会保険料に反映されない | |
| 組合健康保険 | 原則なし | 給与所得を基準とするため、社会保険料に反映されない |
財政の健全化に向けても、金融所得課税の引き上げは重要な意味を持つといえるでしょう。
引用元:厚生労働省|社会保障給付費の推移
背景③:海外と足並みをそろえるため
海外では、アメリカやイギリスなど申告分離課税の所得額に応じて税率が変化する国々があります。
一方で、日本は申告分離課税で一律の税率を適用しているため、海外と足並みをそろえることも金融所得課税の引き上げの要因です。
アメリカやイギリスの申告分離課税は、下表の通りです。
| 国 | 申告分離課税の税率 |
| アメリカ | 0・15・20%の3段階 |
| イギリス | 10・20%の2段階 |
上記の通り、アメリカやイギリスでは段階的課税を採用しており、最大の税率を20%としています。
また、以下のように、日本と同様に申告分離課税で一律の税率を適用している海外の国々も少なくありません。
- ドイツ
- フランス
- スウェーデン など
中国や韓国などの東アジアでは、金融所得の種類によって課税・非課税の扱いが異なります。
すべて非課税の場合もありますが、株式譲渡益は非課税で、配当金は分離課税を採用しているのが一般的です。
金融所得課税の引き上げによる影響が大きい人・小さい人
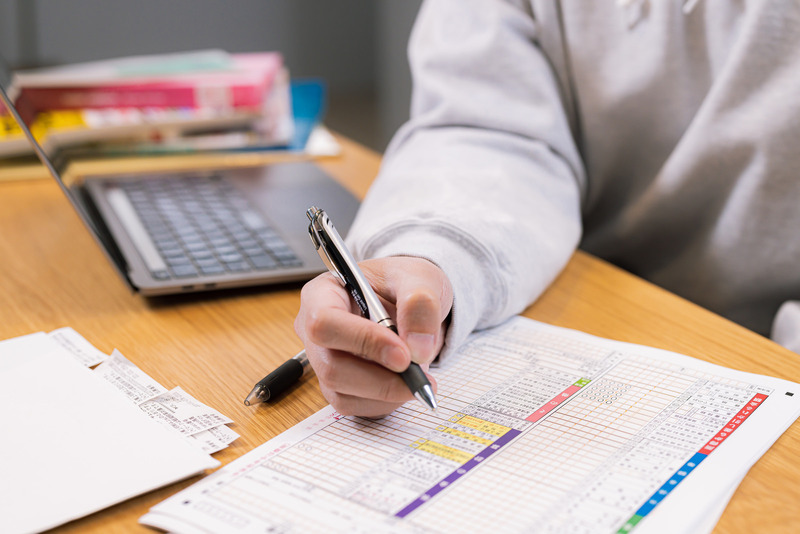
金融所得課税の引き上げによる影響について、以下の2点から解説します。
- 引き上げの影響が大きい人
- 引き上げの影響が小さい人
ご自身の所得状況と照らし合わせながら、チェックしましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
引き上げの影響が大きい人
金融所得課税の引き上げによる影響が大きい人は、「合計所得金額が30億円以上」または「金融所得10億円以上」に該当する人です。
2020年分の申告データを使って財務省が実施した試算によると、追加負担が発生する平均的な所得水準はおよそ30億円からとされています。
金融所得10億円以上の場合については、その他の所得の種類や金額によって影響の大きさが異なるため、注意が必要です。
金融所得課税が追加されるかどうかは、基準所得税額が基準となっており、基準所得税額には給与所得などが含まれます。
つまり、同じ金融所得10億円以上であっても、給与所得など累進税率が適用される所得が多ければ、基準所得税額も高く、影響を抑えることが可能です。
所得30億円超で金融所得課税の負担が増えるかどうか気になる方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】所得30億円超で金融所得課税の負担が増える?追加納税額の計算方法も解説
引用元:財務省|令和5年度税制改正
引き上げの影響が小さい人
金融所得課税の引き上げによる影響が小さい人は、中間所得層です。
中間所得層の定義の仕方はさまざまですが、厚生労働省が公表している2022年の1世帯当たり平均所得金額は下表の通りです。
| 種類 | 平均所得金額 |
| 全世帯 | 524.2万円 |
| 高齢者世帯 | 304.9万円 |
| 高齢者世帯以外の世帯 | 651.1万円 |
| 児童のいる世帯 | 812.6万円 |
また、高所得者であっても、合計所得金額が30億円未満もしくは金融所得10億円未満の場合にも比較的影響が小さいと考えられます。
加えて給与所得など累進課税が適用される所得の割合が多いと、深刻な影響は受けません。
ただし、合計所得金額が30億円未満などのケースでも、所得の構成や金額によって影響は異なるため、税理士など専門家に相談してから判断しましょう。
金融所得課税の引き上げに備える方法

金融所得課税の引き上げに備える方法として、以下の3つを紹介します。
- 新NISA
- 不動産投資
- その他実物投資
金融所得課税の引き上げに備えるには、金融所得課税の対象外に投資する、あるいは金融資産を減らして資産の内訳を変えることが重要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
方法①:新NISA
非課税枠が設けられている「新NISA」を活用すると、一定額までは金融所得課税の影響を受けずに投資ができます。
新NISAとは、投資で得た利益が非課税になる「少額投資非課税制度」のことで、2014年からスタートしました。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれの特徴は下表の通りです。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 投資対象商品 | 一定の投資信託 | 株式・投資信託・ETFなど |
| 非課税保有期間 | 制限なし | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 (成長投資枠は1,200万円) |
|
新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となっており、投資信託と株式投資の両方に取り組める点が大きなメリットといえるでしょう。
方法②:不動産投資
資産の内訳を変えて金融所得課税の影響を軽減したい場合には、節税効果を得やすい「不動産投資」がおすすめです。
不動産投資は給与所得などとの損益通算が認められており、不動産投資の赤字を計上することで節税効果が見込めます。
加えて、不動産の購入費用を一定期間にわたって減価償却できるため、長期的な節税につながるのも魅力です。
その他にも、不動産投資には以下のようなメリットがあります。
- 不動産自体に価値があるため、金融危機が発生しても資産価値が落ちにくい
- インフレ時に物価の上昇と比例して資産価値が高まる
- 安定した家賃収入を得られる
不動産投資は金融機関などから借り入れた融資を使えることから、レバレッジ効果によって効率よく資産形成ができるのもポイントです。
節税効果を得ながら資産形成したいという方は、不動産投資を検討しましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、定期的に不動産投資セミナーを開催しています。
不動産投資について情報収集したいという方は、セミナー参加をご覧ください。
※不動産投資による節税は物件などの条件により効果が異なります。節税を目的とした投資をする際は専門家のサポートを受けながら行いましょう。
方法③:その他実物投資
不動産以外の以下のような実物資産に投資するのも、金融所得課税の引き上げに備える方法として有効です。
- 美術品
- 骨董品
- 高級腕時計
- 金
- 銀
- プラチナ など
不動産と同様に、上記の実物資産は経済や世界情勢の影響を受けにくく、金融危機などの場合でも資産価値を維持できます。
ただし、実物資産は管理費用が高くなりやすいので、ランニングコストを踏まえて検討することが大切です。
加えて、不動産投資は資産保有中に家賃収入が発生しますが、金やプラチナなどは保有時には利益を生ないため、考慮したうえで投資しましょう。
金融所得課税の引き上げに関するよくある質問

金融所得課税の引き上げに関するよくある質問について、以下の2つを解説します。
- 引き上げはいつから?
- 引き上げが決定した背景とは?
安心して投資に取り組むためにも、疑問を解消しましょう。
質問①:引き上げはいつから?
金融所得課税の引き上げは、2025年1月1日以降の所得が対象です。
具体的には、基準所得金額が3億3,000万円を超える際に、超えた部分に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過すると追加負担が発生します。
追加負担が発生する平均的な所得水準は約30億円とされていますが、所得の種類や構成などによっても異なるので注意してください。
質問②:引き上げが決定した背景とは?
金融所得課税の引き上げが実行されたのには、以下のような背景があります。
- 「1億円の壁」問題を解決する
- 社会保障給付費を確保する
- 海外と足並みをそろえる
特に、合計所得金額が30億円以上の方や、金融所得10億円以上の方は影響が大きいと考えられるため、不動産投資に切り替えるなど対策を検討しましょう。
まとめ:金融所得課税の引き上げはすでに始まっている

金融所得課税の引き上げは、2025年1月1日以降の所得について適用されます。
基準所得金額が3億3,000万円を超える場合、超えた部分に一定の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過すると追加負担が発生します。
金融所得課税の引き上げ対策としては、非課税枠がある「新NISA」や減価償却によって節税効果を得やすい「不動産投資」が最適です。
なお、弊社ゴールドトラストの100億円資産形成倶楽部では、100億円の資産を築く節税方法を伝授しています。
効率よく資産形成をしたいという方は、「100億円資産形成倶楽部」をご覧ください。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】2025年以降に不動産価格が大暴落する?価格上昇が期待できる地域も解説
【関連記事】新NISAで上限が見直された4項目|メリットや注意すべき人の特徴も解説
【関連記事】インフレ対策に向いている投資法5選!上手に資産を守る・増やす方法も解説





