所得30億円超で金融所得課税の負担が増える?追加納税額の計算方法も解説

税制の改正によって、変更が生じた事項の1つとして挙げられるのが金融所得課税です。
主に富裕層の所得税に対して影響を与え、所得がおよそ30億円を超える場合に負担が増えるといわれています。
しかし、実際に負担が増える場合にはいくら増加するのかはもちろん、「そもそも、自分にどのような影響があるのか分からない」という方もいるでしょう。
この記事では、所得30億円超で金融所得課税の負担がどれくらい増えるのか解説します。
課税の対象や追加納税額の計算方法はもちろん、引き上げの理由もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
金融所得課税とは

金融所得課税の基礎知識として、以下の3つを解説します。
- 課税の対象
- 引き上げ時期
- 引き上げられる理由
金融資産の種類や日本での保有傾向について知りたい方は、下記の記事もあわせてご参照ください。
【関連記事】金融資産とは?純金融資産との違いや種類・日本人の保有額をわかりやすく解説
課税の対象
金融所得課税の対象となるのは、主に以下の3つです。
- 預金の利子
- 株式・投資信託の配当金
- 株式・投資信託の譲渡益 など
以上のような金融商品から取得した収入に対して、金融所得課税がなされます。
給与所得や事業所得などは累進課税制度となっており、金融所得課税の対象ではありません。
所得の種類によって、課税の方法が異なると認識しておきましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、資産形成や節税ノウハウを学ぶための場である「100億円資産形成倶楽部」を提供しています。
効果的な方法で着実に資産を築き上げたい方は、ぜひ一度お問い合わせください。
引き上げ時期
金融所得課税の引き上げ時期は、2025年分以後の所得からです。
令和5年度税制改正において、措置の導入が決められています。
金融所得課税の引き上げによる影響についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひチェックしてください。
【関連記事】金融所得課税の引き上げはいつから?強化の影響や今からできる対策も解説
引き上げられる理由
引き上げられる理由として、最も大きな要因となるのが「1億円の壁」です。
「1億円の壁」とは、所得税の負担が所得金額1億円までは増える一方、1億円を超えると減っていく状況を指します。
要するに、所得は増加しているにもかかわらず税金が減少するため、高所得者ほど税制面では優遇されているということです。
所得金額による税負担の違いがどのようになっているかは、下表を参考にしてください。
| 平均所得金額(万円) | 平均所得控除(万円) | 平均課税所得金額(万円) | 平均算出税額(万円) | 平均税額控除(万円) | 平均税額(万円) | 所得税および復興特別所得税の負担割合 | |
| 〜100万円 | 79.1 | 64.2 | 14.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2% |
| 100万円〜200万円 | 152.3 | 93.7 | 58.6 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.1% |
| 200万円〜300万円 | 246.7 | 120.7 | 126.0 | 6.9 | 0.1 | 7.0 | 2.8% |
| 300万円〜500万円 | 386.9 | 146.4 | 240.5 | 15.2 | 0.4 | 15.1 | 3.9% |
| 500万円〜1,000万円 | 693.5 | 182.6 | 510.9 | 57.6 | 2.3 | 56.4 | 8.1% |
| 1,000万円〜2,000万円 | 1,381.0 | 217.0 | 1,163.9 | 206.6 | 4.4 | 206.5 | 15.0% |
| 2,000万円〜5,000万円 | 2,919.5 | 231.5 | 2,688.0 | 652.1 | 6.8 | 658.9 | 22.6% |
| 5,000万円〜1億円 | 6,734.6 | 246.8 | 6,487.8 | 1,772.6 | 16.7 | 1,792.9 | 26.6% |
| 1億円〜 | 2億9,982.3 | 489.3 | 2億9,492.9 | 6,905.3 | 141.3 | 6,907.3 | 23.0% |
所得5,000万円〜1億円では所得税の負担割合が26.6%であるのに対し、所得1億円〜になると負担割合は23.0%となっています。
富裕層にとって有利に働く現状を改善するため、税制の改正が実施されるのです。
より公平な税制を実現するために、金融所得課税が引き上げられると認識しましょう。
ミニマムタックスが導入される理由についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】【2025年から】ミニマムタックスとは?影響を受ける・受けない人の違い
所得が30億円を超えると金融所得課税の負担が大きくなる?

前述したように所得が1億円を超えると税負担は減少しますが、約30億円を超える場合には反対に大きくなります。
通常の所得税額を金融所得課税の金額が上回っていると、差額を追加で納税する必要があり、その分岐点が所得30億円です。
また、税負担増加の対象者となる人数は、およそ200〜300人になる見込みです。
所得が50億円の場合だと、負担増加率は2〜3%ほどになると想定されます。
金融所得課税の負担が大きくなる1つの目安が、所得30億円以上の場合であると認識しておきましょう。
なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。
こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。
金融所得課税の強化対象が所得30億円超になった理由

強化対象が所得30億円超になった理由は、投資家が株式市場から離れてしまう恐れがあったためです。
そもそも富裕層は、所得1億円以上で税負担が減少するのを踏まえて、資産形成のために金融所得を増やそうとします。
所得を増やすのが目的であるにもかかわらず、税負担が大きくなるとわかれば、手を引く投資家も出てきて当然です。
投資が鈍化すれば、株式市場の活性化を妨げる要因にもなってしまいます。
また、対象者が日本から海外へ移ってしまう可能性があるのも、懸念点の1つです。
しかし、所得の多い富裕層が優遇される状況は不公平となり、経済格差の拡大にもつながるため望ましくありません。
そのため、まずは特に負担率の低かった所得30億円を超える超富裕層のみが、金融所得課税の強化対象となっています。
今後、課税の対象が広がる可能性もあるため、動向には注視しましょう。
【所得30億円超の方向け】金融所得課税の計算方法

金融所得課税の計算方法として、以下に挙げる2つを紹介します。
- 計算式
- 計算シミュレーション
それぞれ詳しく見ていきましょう。
計算式
金融所得課税の計算式は、以下の通りです。
| {合計所得金額※ −特別控除額(3.3億円)}×22.5%=① ①−基準所得税額(税率15%)=追加で申告納税する金額 |
※株式の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・給与・事業所得・その他の各種所得を合算した金額であり、スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外
金融所得課税を計算するにはまず、合計所得金額から3.3億円を控除し、22.5%を乗じた金額を算出します。
算出した金額が通常の所得税額を上回っている場合には、差額の納税が必要です。
続いて、上記の計算式をもとにした計算シミュレーションを紹介するので、あわせてチェックしましょう。
計算シミュレーション
ここでは計算シミュレーションとして、所得が25億円と30億円の2パターンを紹介します。
所得25億円(事業所得5億円+金融所得20億円)の場合における試算例は、以下の通りです。
| {25億円−3.3億円}×22.5%=4億8,825万円 4億8,825万円−{基準所得税額5億2,020.4万円※1}=−3,195.4万円 |
※1 {(5億円×45%)−479.6万円}+{20億円×15%}
所得25億円(事業所得5億円+金融所得20億円)の場合には、通常の所得税額の方が上回っているため、追加での納税は必要ありません。
所得30億円(事業所得5億円+金融所得25億円)の場合における試算例は、以下の通りです。
| {30億円−3.3億円}×22.5%=6億75万円 6億75万円−{基準所得税額5億9,520.4万円※2}=554.6万円 |
※2 {(5億円×45%)−479.6万円}+{25億円×15%}
所得30億円(事業所得5億円+金融所得25億円)の場合には、通常の所得税額との差額である554.6万円を追加で納税する必要があります。
所得30億円前後においては追納の有無が生じるため、事前に計算して確認しておきましょう。
金融所得課税で除外される主な所得
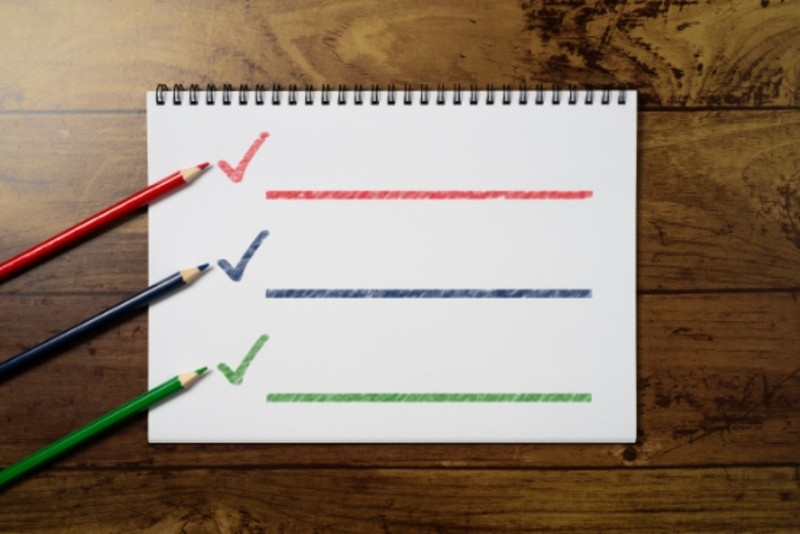
金融所得課税で除外される主な所得は、以下の3つです。
- 新NISA
- エンジェル税制による非課税所得
- 源泉分離課税の所得
それぞれ詳しく見ていきましょう。
除外される所得①:新NISA
新NISAとは、2024年に以前の制度を改正し、新たに始まった非課税制度のことです。
株式・投資信託の配当金や売却益などに対する税金がかからないため、資産形成に活用できます。
日本国内に住んでいる18歳以上の方は、NISA口座を開設すれば誰でも利用可能です。
新NISAでは非課税保有期間が無期限となり、年間投資枠が拡大したため、長期的な運用も可能となっています。
しかし、非課税で投資できるのが1,800万円までと、上限が決まっている点には注意が必要です。
運用できる金額には限りがありますが、誰でも利用できる制度のため、上手く活用しましょう。
新NISAの詳細やメリットについて知りたい方は、下記の記事もぜひチェックしてください。
【関連記事】新NISAで上限が見直された4項目|メリットや注意すべき人の特徴も解説
除外される所得②:エンジェル税制による非課税所得
エンジェル税制とは、スタートアップに対して投資した個人投資家に、税制面での優遇措置をとる制度のことです。
スタートアップへの投資促進を図るために導入され、企業と投資家の双方にメリットがあります。
非課税となる上限は20億円で、投資時だけでなく売却時にも優遇措置を受けられるのが特徴です。
また、保有する株式の売却益を自己資金による創業やスタートアップへ再投資する際には、課税を行わない措置も令和5年4月に創設されています。
令和3年度には、エンジェル税制の確認書が交付された個人投資家数が延べ1万1,929人と、制度の利用者も増加中です。
ベンチャー企業への投資を検討している方は、エンジェル税制の対象となっているかを確認しましょう。
引用:
・財務省|令和5年度税制改正
・中小企業庁|エンジェル税制の実績(投資額・企業数)
除外される所得③:源泉分離課税の所得
源泉分離課税の所得は、受け取る時点で税金が引かれているため、金融所得課税で除外されます。
他の所得とは完全に分離しており、所得を支払う者が一定の税率で源泉徴収することで、納税が完結する仕組みです。
例えば、「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」が対象になっており、確定申告は必要ありません。
課税方式が特殊な場合もあるため、該当する所得がないか事前に確認しましょう。
所得30億円以下でも金融所得課税の負担が大きくなるケース
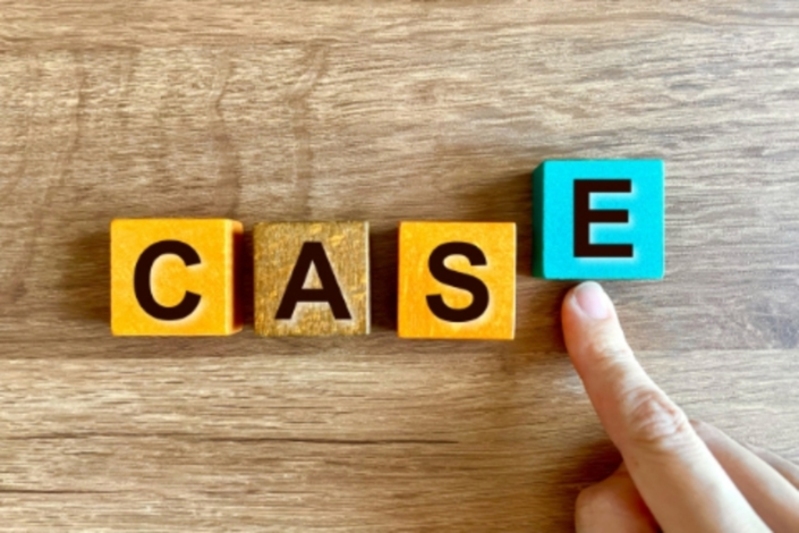
所得が30億円以下の場合でも、内訳によっては金融所得課税の負担が増加するため注意が必要です。
上述したように、金融所得課税によって負担が大きくなるのは、所得30億円以上であることが1つの基準になります。
しかし、所得10億円であったとしても内訳が金融所得のみであれば、税負担増加の対象になります。
金融所得が10億円の場合における試算は、下記の通りです。
| {10億円−3.3億円}×22.5%=1億5,075万円 1億5,075万円−{10億円×15%=1億5,000万円}=75万円 |
所得10億円の場合でも、すべて金融所得によるものであれば、75万円の追納が必要になります。
所得の種類次第で税負担増加の有無にも影響を与えるため、金額だけでなく内訳も必ず確認しましょう。
所得30億円以上で節税したいなら100億円資産形成倶楽部へ

金融所得課税の引き上げは、資産形成に大きな影響を与える出来事です。
特に所得30億円を超えると税負担は増加する可能性が高いため、節税対策もより重要なポイントになります。
弊社の「100億円資産形成倶楽部」では、100億円の資産を築く節税方法を伝授しています。
誰でも実現できる節税ノウハウと実践方法を伝えており、設立から約5年で運用資産が総額300億円と実績も豊富です。
専門家のアドバイスをもとに再現性の高い方法で資産を形成したい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
所得30億円超の金融所得課税に関するよくある質問
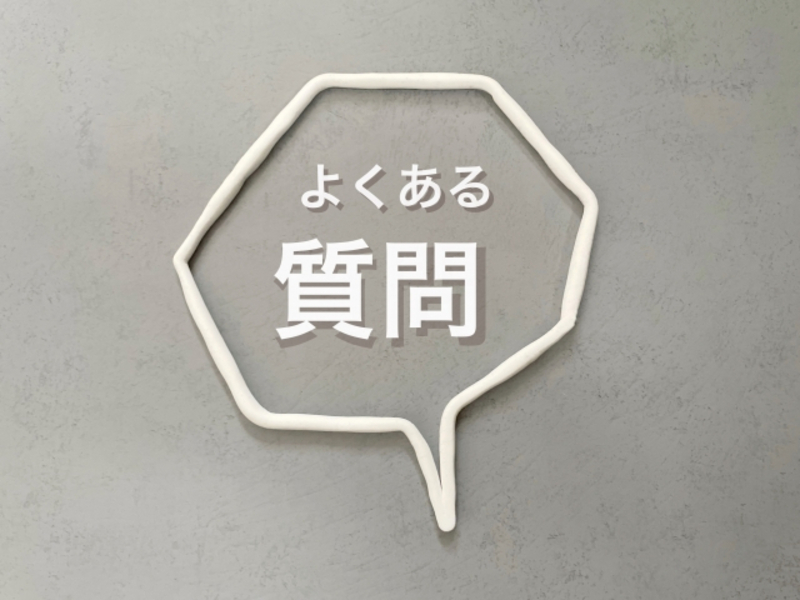
所得30億円超の金融所得課税に関するよくある質問は、以下の2つです。
- 税負担はどれくらい増える?
- いつから引き上げになる?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
質問①:税負担はどれくらい増える?
所得が30億円(事業所得5億円+金融所得25億円)の場合には、税負担が通常の所得税額と比べて554.6万円増えます。
しかし、所得の内訳によっては負担額が変動するため、上述した計算式を参考に試算してみてください。
また、税負担が増えるのは所得30億円超が1つの基準ですが、場合によっては所得10億円でも増加するので注意が必要です。
給与所得や事業所得ではなく、主に金融所得に対する課税が引き上げられると認識しましょう。
質問②:いつから引き上げになる?
金融所得課税の引き上げが始まるのは、2025年分以後の所得からです。
令和5年度税制改正において引き上げが決められており、現在すでに対象の時期となっています。
金融所得課税の引き上げにおける影響を受ける可能性がある方は、早急に確認しましょう。
まとめ:所得30億円超の方は金融所得課税の引き上げに要注意

金融所得課税の引き上げで最も影響を受けるのは、所得が30億円を超える方です。
以前と同様の所得であったとしても、税金が増加する可能性もあるため、所得30億円超の方は追納が発生しないか確認しましょう。
なお、弊社が運営する「100億円資産形成倶楽部」では、資産形成のプロが100億円の資産を築く節税方法を伝授しています。
豊富な実績とノウハウにもとづいたサポートにより、節税および資産形成を実現したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!
【関連記事】金融所得課税とは?日本と海外を比較!最新の動きや引き上げのリスクも解説
【関連記事】【将来に備えて】資産運用セミナーに参加するメリットとは?注意点も解説
【関連記事】資産家とは?資産家になるための秘訣を大公開!





